歪んだ夜のむこうへ ―海を乞う人―
幼い女の子が世界を手に入れるのは簡単だ。
甘い父親がひとりいればいい。
欲しいものはいつだって、欲しがる前から揃っていた。
当然のように清潔な服がたたまれ、座るだけで暖かい食事が出てきた。
愛はねだらずとも献上され、満足はむこうからやってきた。
でも、それはきっと誰でも同じだったと思う。
家庭は最も小さな社会、人が最初に属する国家で、そして子供はいつも自覚のない専制君主だ。
だけどそのうち気付くのだ。
本当に欲しいものは、いつも世界の外にあることを。
そして世界の外には、誰の助けも無いことを。
5歳のとき、初めて海に行った。
視界に収まりきらない紺碧に歓声を上げ、眼に痛いほど白い波頭を追いかけてはしゃぎまわった。
一日じゅう遊んで疲れ果てた私が、眠い目をこすりながら水筒に海水を詰めるのを、両親は不思議そうに見ていた。
私が何をしたいのか解らなかったのだろう。
家に帰ってすぐ私は、わくわくしながらグラスにそれを注いで覗き込んだ。
だけど、グラスの中に閉じ込められた海は、ちっとも青くなんかなかったのだ。

茂みをがさがさとかき分けて歩むその音は、野良犬にしては大きすぎた。
郁恵は訝しんでスケッチブックから顔を上げる。ここで絵を描きはじめてしばらく経つが、そう人が来るような場所ではない。
市街地と海岸とを隔てる緩衝緑地帯――ただしおざなりな防風林とはわけが違う。
もともと小さな山だったものを、市が『海の見える自然公園』として開発した地域だ。林道があちこちに通り、休憩所も用意されている。
郁恵が陣取っているここは、眼下に浜辺を一望できる気持ちのいい斜面だ。ただし上の遊歩道から外れ、深い藪を漕いできた場所にある。
背後を背の高い草に囲まれ、通行人からも見えないこの隠れ家を、彼女はとても気に入っていた。
それなのにどうだろう。
犬を散歩させる人だって、普通ここまでは来ないのに。
次第に近づいてくる音に彼女は警戒したが、まず踏み出したスニーカーの足、次いでひょっこりと出てきた顔の幼さに少しだけ安堵した。
ずいぶん可愛い顔をした男の子だったからというのもある。
「あ、人がいた! ……って、へえ、ここ広いや」
突然現れた少年は、そんなことを言って辺りを見回しながら、苦労して藪から抜け出した。
知らない人間と鉢合わせたと言うのに、気後れするふうな態度は微塵もない。
戸惑う郁恵の様子をよそに、草切れで汚れたトレーナーの肩をはたきながら彼はこう言った。
「あのさ、月村知りませんか? まったくどこ行っちゃったんだか」
前置きと説明の欠如した問いかけに、どう答えていいか解らず言葉に詰まっていると、少年は何を勘違いしたのかこう続けた。
「あれ? えっと、女性に話しかけるときは名乗るのが礼儀だっけ? オレ生島って言います」
よろしく、とぺこりと一方的に頭を下げる。
一瞬の間を置いて、郁恵は思わず吹き出してしまった。
ずいぶんマイペースな子供だが、彼は彼なりに礼を尽くしているようだ。
それをあますところなく表に出しているので、なおさらなんとなく許せるイメージがある。得な性格だなと好感的な意味で思った。
「初めまして、生島くん。……月村……って言うのは何? お友達?」
「オレのなんだ」
にこにことそう即答する。
妙な言い回しだったが、要は同意だろうと郁恵は解釈した。
言葉が足りないのは男の子にはよくあることだ。
「その月村くんとはぐれちゃったのね。どんな子なの?」
「えーと、オレと同い年で、大人しそうな感じで……どう説明すりゃいいのかなあ? 人の顔って」
両手で人の輪郭を形作るようにしながら彼は、ふと郁恵の膝のスケッチブックに目を留める。
「あれ、おねえさん絵描いてるの?」
「ええ。いい景色でしょ、ここ」
少年が興味津々といった顔つきで身を乗り出す。郁恵はくすりと笑い、見やすいようにスケッチブックを差し出した。
誰かが外で絵を描いていると、人はどうしても興味を持つものらしい。

「うわ、上手! すげー綺麗だ」
少年らしい正直な感嘆の声を上げる。絵で食っている郁恵には聞きなれた台詞だが、もちろん悪い気はしない。
「このへんとか細かいなー。何で描いてるの?」
「今日は色鉛筆ね。たまには絵の具持ち出して、水彩で描くこともあるけど」
すげーすげーとスケッチブックをめくる少年に、郁恵は気をよくしてこう続けた。
「あなたのお友達の、月村くんだっけ、その子の似顔絵でも描いてみる? もし似てる子を見つけたら、お役に立てるかも知れないし」
少年は顔を上げて思案し、しかし苦い顔をしてスケッチブックを返しながら言った。
「でもオレ、絵上手くないから描けないよ。見て描いたってそっくりには描けないのに」
「そうね。見たままを描くのって、難しいわよね」
しみじみと同意する郁恵の言葉に、少年は小首をかしげた。
「え、おねえさんは上手じゃん。すごいリアルだし」
そう言って眼下の海岸と、郁恵のスケッチブックを見比べる。確かにそれは今しがた、彼女が描いていた風景だ。
「ありがとう、でも……なんて言えばいいかな」
相手に理解してもらえるかどうか、半信半疑のまま郁恵は言葉を紡いだ。
「綺麗だなあと思ったものを、なるべくそのまま、絵に描こうとするんだけど……
本当にそのまま、っていうのはどうしたって無理なのよ。むしろ、描くそばから別のものになってしまう。
似ているものなら描けるけど……そこまでなのよね。この絵の中には、本当の海が無いのよ」
「……んー?」
よくわかんないけど、そんだけ描けたらオレなら大満足だよと少年は笑い、おまけのようにこう続けた。
「まあ確かに、絵の中の海に飛び込んで、泳ぐことはできないけどさ」
「男の子らしい意見ね」
笑顔でそう返しながら郁恵は、今のやりとりを大人が横で聞いていたら、きっとこう思うだろうと考えた。
――『子供にはやはり、ものの喩えが解らない』
でも、と彼女は内心で苦笑する。少年の言葉は、実は自分の思いを端的に表すものだった。
そうだ、それが限界だ。絵の中の海では泳げない。
郁恵が絵を描き始めた理由はただひとつ。すべてを手に入れたい、その思いだった。
たとえば晩夏の夕焼けの、瞼の裏まで燃えるような鮮紅。
たとえば冬の静夜の、骨まで凍るみっしりとした藍色。
そんなにも美しく目に映るものを、なぜ閉じ込めて持ち帰ることができないのか。郁恵にはそれが理不尽に思えて仕方なかった。
しかし、ここで毎日のように海を描いて家に持ち帰っても、絵の中には海のひとしずくさえ再生できない。
どれだけリアルに描いたところで、絵の中にあるのは画材と紙で構成された、”海”を表す記号だけだ。
当然だ、絵は二次元の存在なのだから。そう理解していてもどうしても欲しい。
あるとき突然に絵の中から、生臭いような磯の香りが、風に散るかもめの声が、指先に冷たく遊ぶ潮水が、わきあがって溢れてきて欲しい。
……少し病的だと、自分でも思っている。
「そういえば」
軽く頭を振って妄執を追い払いながら、郁恵は言った。
「あなたが探しているお友達は、今日はどんな服を着てるの?」
気持ちよさそうに海風に身を任せ、浜辺を見下ろしていた少年は、一瞬きょとんとしたがすぐ理解の色を浮かべた。
「そうか、顔が解らなくても、服で見分ければいいんだ」
「私、今ちょっと画材出しっぱなしだから、遠くまでは行けないけど」
トートバッグの上に散らばる色鉛筆を指差してから言葉を続ける。
「この近くだけで良ければ、探すの手伝ってあげるわ。それでもし見つけたら、事情を話してここに引き止めておくし。
君はほかのところを探して、それでも見つからなかったら、またここに寄ってみなさいよ」
「いいの? それ助かるや、ありがとう」
ぱっと笑うと、この子は本当にきれいな顔をしている。なんとなく嬉しくなって、郁恵もとりあえず笑った。
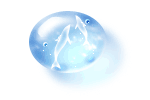
生島と名乗る少年が去ったあと、郁恵は少しあたりを片付けてから立ち上がった。
貴重品だけは持っていこうとバッグの中を探り、財布と携帯電話を取り出したところで、手が止まる。
……バッグの中に、”あれ”が無い。
他のものを取り出し、覗き込むようにして底を探る。内ポケットや着ている服のポケットも探る。
それでも見つからず、今度は座っていた付近の地面や、歩いてきた藪の中を這うようにして探す。
だが、やはり見つからない。
郁恵は困ってあたりを見回した。どうやらどこかに落としたらしい。
決して目立つものではないし、どこで落としたのか心当たりもない。探すのはきっと苦労だろう。
だけど、と彼女は溜息をつく。
手元に無いと割り切ってしまえば、奇妙な開放感がないでもなかった。そもそも必要ないものなのだ。
私はそれを二度と使わない――使わないことによって起きる事実をいつも確認したいがために、それを持ち歩いていたに過ぎない。
もし他の誰かがそれを見つけても、どこで使うべきものなのか、解る人間がいるはずもない。
誰も知らない。誰も知らないのだ。
私だけが知っていればいいことなのだ。
迷ったあげく、郁恵はとりあえず藪をかき分けて上の遊歩道に出た。
気持ちはまだ決めかねているけれど、どこにあるのか解らないのは、やはり少し気持ちが悪かった。
しかし遊歩道に出て、探しながら歩き始めたその時、彼女は正面からやってくる小さな人影に気付いた。
頭の中で思わず、先程の少年から聞いた情報を反芻する。
黄緑色のチェックのシャツ。
年齢も、あの子とちょうど同じくらいに見える。
タイミングがいいのか悪いのか解らない、そう思いながら郁恵は少年を呼び止めた。
「ちょっとごめんなさい」
上げられた顔は少し焦っていた。この子も恐らく、相棒を探して歩き回ったのだろう。
「間違ってたら悪いんだけど……あなた、月村くんじゃない?」
「……そうですけど」
少年は戸惑い、その表情は警戒に変わる一歩手前だ。生島というあの子とはずいぶんタイプが違う。
郁恵が急いで事情を説明すると、少年はやっと安心したように笑った。
「ありがとうございます。着いて早々はぐれちゃって……よく知らない場所だし、どうしようかと思ってました」
「あら、あなたたち、この辺の子じゃないの?」
聞けば隣の市の中学生だと言う。しかし郁恵には、彼らがそんな遠くからわざわざ遊びに来た理由が思いつかない。
普段の客層からして、地元のお年寄りや幼稚園児が関の山、という地味な公園だ。特にこの付近は、眺めこそいいのだが管理が悪くさびれている。
場所によっては、粗大ゴミや不燃物がこっそり不法投棄されている始末だ。中学生に面白い場所だとはとても思えない。
……微かな疑問を、郁恵はまあいいや、と心の隅に転がしておいた。彼らにすればちょっとした探検ごっこのつもりなのだろう。
「じゃあ、私の荷物が置いてあるところに案内するわね。そこであの子を待ちましょう」
郁恵は少し迷ったがそう言った。
本当はこの少年だけを待ち合わせ場所に行かせ、自分は探しものを続けてもいい。
だが、慣れない場所で友人とはぐれた少年をひとりで置いておく罪悪感と、あれに対しての決めかねる感情がまだ少しあった。
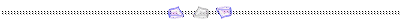
「……絵がご趣味なんですか?」
郁恵の隠れ家に到着した月村という少年は、画材を見て控えめにそう言った。
全身で見せてくれとねだったあの生島という少年とは違って、あくまでも礼儀正しい。世間話で場をもたせようとする大人のような態度だ。
その背伸びが可愛らしく思えて、郁恵は逆に少しからかってやりたい気分になった。
スケッチブックを渡しながら、さらりとこう付け加える。いつもなら初対面の相手には気恥ずかしくて言わないのだが。
「趣味っていうか仕事なんだけどね。童話雑誌で、表紙とかちょっとした挿絵とか描いてるの」
「え、本物の画家さんなんですか……!」
スケッチブックをめくる手が止まり、驚いた瞳がまっすぐ彼女を射抜く。
郁恵は思わず赤面してしまい、手を振りながら少し慌てて言った。
「画家ってそんな、物々しいものじゃなくって。ちょっと描かせてもらってるだけよ」
面と向かって驚かれると、何か居たたまれないものがある。何よりも彼女自身が自分の立場に慣れていなかった。
「別にそんなすごいことじゃないのよ。雑誌も小さな出版社のだし……。
あ、でもね、その挿絵が少しづつ好評をもらって、こんど絵本とか出さないかって誘われてるの」
「それってやっぱり、すごいじゃないですか」
微笑みながら少年が言う。ありがとう、と礼を返すと、また少し頬が熱くなるのが自分でも解った。
「どんな話の絵本なんですか?」
「えーと、まだ構想中なんだけどね」
郁恵は少年からスケッチブックを受け取り、最後のほうに挟まっているイメージボードを取り出して見せた。
絵を覗き込んだ少年が、へえ、と声にならない微かな呟きを漏らす。
――天井ばかりが高い、石造りの冷たい宮殿で、グラスを片手にうつむいて途方に暮れる幼い王女――
描いた彼女にとっては、懐かしいとすら思える原風景だった。
「……綺麗だけど、何だか沈んだ感じですね」
少年が言葉を選びながら感想を述べる。絵についての説明を求めたい気持ちなのだろう。
「そうね、これが物語の冒頭のシーンなんだけど……」
少しおどけた風に、芝居がかった調子で彼女は語りだした。
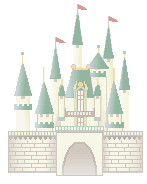
「”むかしむかしあるお城に、一人のわがままな王女さまが住んでいました。
王女さまはある日、臣下のものたちを集めてこう言いました。
『海の水は、なぜ容れ物に汲んでしまうと青くなくなるのか? 誰かこのグラスに、海の水を青いまま持って参れ!』”
……続きはまだ考えてないんだけど、まあ、そういう感じのストーリーね」
「うーん……なかなか難題を言う王女さまですね」
ボードに描かれたグラスと、眼下に広がる海辺を見比べて、少年は苦笑するように呟いた。
「王女さまはどうして、そんな無理なことを言い出したんですか?」
「彼女自身は、自分が無理なことを言ってるとはあまり思ってないかも知れないわ」
「本物の海を見たことがないとか……」
「あるんだけど、それ以上に欲しい気持ちのほうが強いのよ、きっと」
郁恵は空を見上げ、先程と同じ口調で、思いつくままに続きを呟いた。
「”王女さまは小さいころ、父王さまとそのお妃の母上さまに、海に連れていってもらったことがありました。
その思い出だけが……今の王女さまの頼りでした。
だから、あの日と同じ色をした海を、どうしても手元に持っていたかったのです”」
「……王様とお妃さまは、今はどうしてるんですか?」
不吉な匂いを嗅ぎ取ったのだろう、少年の質問は慎重だ。
郁恵は続けた。
「……”王女さまは、今なら母上さまの気持ちが解る気がしていました。
父王さまはいい人なのだけれど……ただ底抜けに楽天家で、遊び好きで、派手好きで……
責任を考える、自制をすることが全然できない人だったのです。それは女の人に対してもそうでした”」
つれづれと話すうちに、現実が少しづつ勝手に混入してくる。郁恵はそれを自覚していたが、気にせずに続けた。
横目でちらりと伺えば、そんな話を聞かされる少年のほうは絶句して困っている。
心の中で悪戯っぽく舌を出して、彼女はまた話を続けた。
「”よそに女の人がいたのは確かなのですが、王女さまや母上さまのことを見捨てたわけではなく、”……
……母や私を愛してないんじゃなくて、それだけじゃ足りなかった、そういうことだと思うわ。
自分への愛を無制限に、無責任に集めたい人なんでしょうね。きっと」
「…………」
郁恵は眼を伏せる少年の顔を覗きこみ、その困惑を優しくからかうように、声をあげて笑った。
「ごめんなさいね、何をつまんない話してるんだか」

こんなことはどこにでもある話だ。
見知らぬ子供相手に同情を引きたいわけでもない。
ただ、どこか困らせてやりたいような、いじめまわして可愛がってやりたい雰囲気がこの少年にはある。
それでつい要らないことまで言ってしまった。
「あんまり深刻に受けとらないでちょうだいね。クリエイターは自分の身内さえネタにする、罰当たりな職業よ。
もっとも、今の話はとても絵本には起こせないわね……レディコミじゃないんだからさ」
冗談っぽくそう言うと、少年はやっと表情を緩めた。
だがまだ少し落ち着きがないようだ。目線をさまよわせて他の話題を探す様子がなんともいじらしい。
「えーと、じゃあ物語の続きは……どうするんですか」
「そうね、どうしようか」
郁恵は立ち上がり、両腕を上げ、軽く背筋を伸ばしながらこう言った。
「王女様の望みは叶うのか、それとも叶わないのか……
ただ言えるのはね、この王女さまも、”汲んできた海が青くない理由”についてきっと自分で推測してると思うの。
光の反射がどうとか、科学的な理由じゃなくて……幼い王女さまが考えた、自分なりの理由がね……」
幼いあの日、グラスの中に閉じ込められた海は、ちっとも青くなんかなかった。
海に行こうと言い出したのは父だ。
本当に楽しかったあの旅行に、突然行こうと言い出したのは父だ。
『驚かせようと思って黙ってたんだ』と、浜辺の有名ホテルのチケットを見せて、私と母に歓声を上げさせたのは父だ。
急に愛人の都合が悪くなって行けなくなった旅行を、私と母のご機嫌取りに転用したのは父だ。
後になって真相がばれて、言い争う両親の横で、私は虚ろな色をしたグラスを見ながら子供なりに納得したのだ。
ああ、だから青くないんだ、と。

がさがさと大袈裟に音を立てながら、その人は迷わずにまっすぐこちらに向かってくる。
郁恵と少年が振り向くと、相手はちょうど藪から顔を突き出したところだった。
「いたーー!!」
こちらを見ると同時に大声をあげたその子は、茂みから足を抜くのももどかしく、月村という少年に抱きついた。
「どこ行ってたんだよもう! オレすっごい捜したぞ!!」
「よく言うよ」
少しきまりが悪そうに、呆れたように、抱きつかれた少年は言った。
「勝手にどんどん先に行っちゃってさ。このままじゃはぐれちゃうって、僕は何度も言ったよ」
だが言われたほうは我関せずだ。いやあ良かった良かったと、相手の頭を嬉しそうにぐりぐり撫で回している。
解りやすい2人の相関図に、郁恵は思わず微笑んだ。
「おねえさんも有難う、助かったよ! 無くしたらどうしようかと思ってた」
「良かったわね、本当に」
郁恵の返事にうんうんと頷きながら、彼はふと思い出したように、腕の中の少年にこう話しかけた。
「そうだ月村、おまえを捜してる間にいいもの拾ったんだ。見せてやるよ」
ポケットをごそごそと探り、赤いふさ飾りのついた物体を取り出し、眼の高さに掲げて見せる。
「RPGのアイテムみたいでかっこいいだろ? ほら」
得意げにそう言う。確かに彼くらいの歳の子には、アンティークと言うよりもファンタジー的な感覚の品物なのだろう。
錆の浮き具合も美しい、その品物は、古びた大きな鍵だった。
「でも生島、それって……」
「……棒鍵っていう種類ね、それは」
少年の言葉を遮るように郁恵は言った。
「昔よく使われてたタイプよ。いま使われてる鍵は平べったいのが多いけど、それは真ん中の軸が棒みたいになってるでしょ?」
「へえ、よく知ってるね」
「私の家も古いから」
「だけど生島」
うずうずと何か言いたげだった少年がやっと口を挟んだ。
「鍵っていうのは大事なものだろ? もしかしたら誰かが捜してるかも知れないよ。公園の管理の人に届けたほうがいいんじゃない?」
「えええ」
いかにも不満そうな声がその意見を否定する。
「だって藪の中に落ちてたんだぜ? 絶対捨てられてたんだって。もう使われてないよ」
「でも……」
その言葉を再び遮るように、郁恵は静かに質問した。
「あなた、それを持って帰りたいの?」
彼女の妙に生真面目な問いに、少年はちょっと不思議そうな顔をしたが、すぐに大きく頷いた。
「気に入ったの?」
「すごく気に入った」
「どうしても欲しいの?」
「欲しい」
自分の欲求を隠すことも、躊躇うこともせず、そのための努力も惜しまない。
痛々しいほど自分を偽らないその顔に、少しの共感とそれゆえの重苦しい痛みを覚えて、郁恵は下を向いた。
それは彼女がずっと持ち歩いていた、ついさっき落としてしまった鍵だった。

母が交通事故に遭い、聴覚をほとんど失ったのは2ヶ月前のことだ。
足にも少し障害が残って、非常にゆっくりとしか歩けない。
身の回りのことくらいは一人でできるけれど、当然もう以前のように、かいがいしく他人の世話を焼くことはできない。
そして、自分への愛を解りやすい形で示すことのできない女を、父は必要としていない。
以前よりいっそう留守にすることが増えた父の鞄から、署名と捺印の済まされた離婚届を見つけて、私は知った。
本当に欲しいものは、いつも世界の外にあることを。
そして世界の外には、誰の助けも無いことを。
自力で手に入れなければいけないのだ。もう誰も、それを与えてはくれないのだから。
事故のあと、足を悪くした母のために新しく家を借りていた。
古い家だったけど、以前に住んでいたお年寄りがバリアフリー工事をしていたのと、階段のない平屋造りなのが便利だった。
庭の物置には地下蔵があったけど、大家からは、前の住人が鍵を無くしてしまって開かないと聞いていた。
だけど数日前、母が通院で留守にしている間に、押入れの隅に落ちていた鍵を父が発見したのだ。
「お宝が出てきたらどうしような?」
重たい扉を開けながら、子供のようにはしゃいで彼はそう言った。
もし何か面白いものが出てきたとしても、それを家に飾るつもりはないのだ。
どこかの女性と構えた新居に、意気揚々と、それを持っていくつもりなのだ。
「ちょっとこれ持っててくれ、懐中電灯を付けるから」
地下の薄闇に降り立った父が、そう言って私に鍵を渡したとき、考える前に身体が動いた。
彼に勢いよく体当たりして、埃っぽい床に突き転がしたその隙に、階段を駆け上がって扉を閉めて鍵をかけた。
状況がよく掴めず、おろおろと声を上げながら扉を叩く音を無視して、そこらにあった古い布団を扉の上にどさどさと重ねた。
その上や周囲に、苦労して、古箪笥や古新聞といった重たいものを山のように積み上げた。
そうしてしまうと、嘘のように静かになった。
がらくたの山を前に、肩で息をしながら、ぼんやりとこう思った。
どうして私の欲しいものは、いざ手に入れてしまうと、その色を失うんだろう。
それでも私は、海を描き続けるのを、止めることはできない。
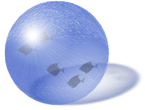
現実に意識を引き戻してみれば、少年たちはまだ言い争っている最中だった。
郁恵はつい先ほど交わした会話を思い起こす。彼らは確か、隣の市に住んでいると言っていた。
この公園にも、そう頻繁に来るわけでは無いらしい。
ここで名前も聞かずに別れてしまえば、恐らく、もう二度と会うことは無い。
「おねえさんはどう思う?」
生島という少年の顔がくるりと向き、こちらに意見を求める。
悪魔はきれいな顔をしているというのは、本当かも知れない。
物置の床に耳を押し当てればごくかすかに、
かりかりと壁を掻く爪の音が、疲弊しきったすすり泣きが、
まだ聞こえるのだけど。

「……まだ考えてるのか? 月村」
海岸を見下ろしながら歩く遊歩道で、夕日を片頬に浴びて生島が振り向く。
「おねえさんも言ってたじゃんか。痛みは少ないけど、そうとう古い鍵のはずだって。もう使われてないに違いないってさ」
赤いふさ飾りを持ってくるくる振り回しながらそう言う。
僕は内心で溜息をついた。
ものがものだけに、慎重になったほうがいいと思ったのだけど……まあ確かに考えすぎか、と自分を納得させる。
前を見れば、生島は少し先に行ってしまっている。
いい物を拾った日はいつもそうだけど、彼はとても上機嫌で足取りも軽い。ついていくのが少し大変だ。
「ねえ、生島」
歩みを緩めてもらいたい一心で、僕は声をかけた。
「君が来る前に聞いたんだけど、さっきのあの人、こんど絵本を出すんだって」
「へえ? すごいじゃん」
「で、そのストーリーを構想中らしいんだけど……君ならこの続きをどう書くかな」
「? どんな話だ?」
生島が立ち止まる。
僕はやっと彼に追いつき、軽く乱れた息を整えながら聞いた話を伝えた。

「……”王女さまはある日、臣下のものたちを集めてこう言いました。
『海の水は、なぜ入れ物に汲んでしまうと青くなくなるのか? 誰かこのグラスに、海の水を青いまま持って参れ!』”……
で、この続きをどうしようかって話なんだけど」
「……うーん?」
生島は大真面目に、腕を組んで考える。
でもその表情は、続きを考えているというよりは、何かが引っかかっているような表情だ。
「どうでもいいけどさ、その王女さま……グラス一杯で満足なわけ?」
「え?」
予期しなかった質問に、僕は思わず間の抜けた声を出した。
「気持ちは解るけどさ、王女さまなんだろ? グラス一杯なんてしみったれてないか?
もっとこう……あ、そうだ」
生島は急に納得がいったように手を打ち、にやにやしながら僕の顔を見た。
「じゃあこう言えばいいんだ。見てろよ」
そう言うと僕に向きなおり、すっと居住まいを正し、優雅にお辞儀をする。その姿は妙に決まっていて、僕は思わずどぎまぎする。
モデルをやっているせいか、彼はこういった、人に見られることを意識した動作がとても板についている。
「……”承知いたしました、王女さま。
しかし、王女さまに捧げるものならばやはり、容れ物も一流でないと。
そのようなちっぽけなグラスではなく、もっと貴方に相応しい器でないといけません”」
生島はお芝居の一場面のように、胸に手をあてて恭しくひざまずいた。
そして、さっと手を上げた。
「”ご覧下さい、王女さま。
あなたのために、世界で一番大きな容れ物に入れました。
ここから見えるすべてが、あなたのものでございます”」
生島の手の示す先には、
夕焼けの薄闇の中でも、まだ蒼さを失わない綺麗な海原が、静かに波打っていた。

「……って言うのはどうだ?」
自分の機転に浮かれたように、うきうきと生島は笑って見せる。
僕は言葉が出ない。呆気にとられてしまった。
ただ、存分に呆れたあとでやってきた感情は……いろいろな感情が無闇に入り混じった、わけのわからない切なさだった。
「それは……ずるいよ」
うまく言葉が出ず、僕はやっとそれだけ言う。
ずるいよ生島。
そんなことを言われて、君の所有物はどんな顔をすればいい?
「やっぱ、ずるいかなあ?」
へへ、と軽く笑って彼は、また足取り軽く歩き出す。その背中は草や泥であちこち汚れている。
それを見ながら、僕はこっそりと祈る。
神様は信じていないから、永遠に一番近いはずの、この海と太陽に祈る。
その背中がいつまでも楽しそうならいい。
そして僕も、いつまでもそれを見ていられたらいい。
叶うはずもない願いを、そうと知りながら抱きしめて、僕は自分を甘やかす。
そして彼のあとについて、今はただ、帰路を急いだ。

Fin.
 
|