春の嘘
4月1日はエイプリールフール。
毎年この日、西署は頭が痛かった。
何故なら、この日に限り、事件の通報が増えるからである。
もちろん大半はエイプリールフール仕様の冗談通報なのだが、中には冗談と解らないような悪質なものもある。
さすがにジャンク関係の偽通報は無いのだが、そこの通りで撃ち合いをやっています、なんて通報は必ず来る。
嘘じゃないかと思っても、仕事だから行かざるをえない。
そして行ってみたら、子供が水鉄砲を撃ち合っていた、なんて事を目撃する破目になるわけで。
最初のうちこそ苦笑いが浮かぶが、何度も続くとこういう冗談は笑えなくなるものだ。
それに、嘘に振り回されて人が少なくなった所で、本当の事件が起こったりしたらかなわない。
故に4月1日、
この日の砂城西署には、奇妙にぴりぴりした雰囲気が漂っていた。
「嘘は嫌いだ…」
黒羽 高はぼっそりと呟く。
相棒の白鳥香澄がおそるおそる見上げると、普段は殆ど無表情に近い白い顔に、あきらかに『不愉快』という文字が浮かんでいるのが読みとれた。
うへぇ〜…機嫌悪い。
白鳥はそっと首をすくめる。
普段ほとんど感情を表に出さない黒羽が、これほど不機嫌になるのも珍しい。
確かにさっきの通報はかなり悪質だった。
何と言っていいのか、まあ簡単に言っちゃうと一種の狂言誘拐だったのだ。
悪ふざけがすぎたガキ共は、最後に
「ウ・ソ。エイプリールフール♪」
とでも言えばいいと思ったらしく、誘拐事件をでっち上げ、ポスターで顔を知っている黒羽を、名指しで呼び出したのだった。
しかし…なんて言うかその…。
ガキ共は仕事中のコウが、どんな感じなのかは、まったく解っていなかった。
奴らが知っていたのは、ポスターで微笑むコウか、広報の協力をしている時の穏やかな『善良な市民向け』のコウか、どちらかだろう。
穏やかに話す、絶対に安全な、素晴らしく見栄えの良いお巡りさん。
そう思っていたんだろうな。
でも犯罪者に対峙する時のコウは、そうじゃない。
触れれば切れる、研ぎ澄まされた抜き身のナイフを連想させる剣呑さ。
銃を撃つことだって、躇ったりしない。
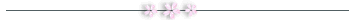
もちろん最初に現場に到着した瞬間、白鳥にはこれが冗談であることが解った。
古いビルの下に集まっていたのは、16〜18歳位のガキばっかりだったが(でもオレとあんまり年変わらないんだけどな…ため息)真剣な声で事件の通報をしておきながら、そいつらの誰にも緊張感の欠片もなかった。
また四月馬鹿かよ。
こいつら、まんまと警官を騙して、してやったりと思っているんだぜ。
四月馬鹿で許されなくても、見間違いでした、とか、勘違いでした、とか言うつもりなんだ。
たちの悪い冗談にオレはもちろんムカムカしたが、ふと隣を見ると、コウの姿勢はまったく変わっていなかった。
「建物の上に犯人が?」
コウの言葉に、少女の一人が半分笑いを貼りつかせながら、それでも答える。
「はい。私の妹をいきなり攫って、ここに逃げ込んだの」
コウ、こいつらの冗談だってば、と言いかけたが、その前にスーツをひるがえし、コウはビルの中に飛び込んでいった。
お、おいおい。
もちろん即座にオレも後を追いかけたが、特別に訓練されたコウの足は、恐ろしく速い。
舌打ちしながら、かなり遅れて階段を駆け上がると、一番上の階についたコウは、既に左腕を上げて例の銃を構えていた。

ソウドオフショットガン。
銃身長28センチ。
通常45センチ以上あるショットガンの銃身を短く切りつめた形。
反動を軽減するために、ストックの代わりにピストルグリップが取り付けてある。
コウしか持っていない、コウの為だけの、特別な銃。
その重い銃を左腕一本で構え、すらりと立つ姿には、一見の価値があった。
駆け上がってそれを見たオレだって、一瞬ボケッと見蕩れちゃったくらいだ。
奴ら、絶対これが見たかったに違いないと思う。
綺麗だもんなあ…。
事件じゃないことが解っていたオレは、つい呑気にそんな感想をいだいていたのだが、次の瞬間ぎくりとした。
コウがまったく銃口を下げない。
銃が向けられている奥の部屋には、確かに誰かが潜んでいた。
二人ほどだろうか。
ごそごそと動いていて、やはりまったく緊張感が感じられない。
多分コウのこの姿をカメラにでも収めれば、彼らの任務完了という所なのだろう。(絶対写真を、後で高く売るつもりに違いない)
しかし彼らの思惑に反して、コウはその場を冗談にしなかった。
「人質を放せ」
「コウ…」
コウの鋭い声にドキドキしながら、オレはそっと声をかける。
「銃持ってるぞ〜」
まぬけた様な声が、奥から響いてきた。
ば、馬鹿野郎!
オレは思わず奥の暗がりを睨んでしまう。
ここの空気が読めないのかよ。今コウは、完全にこれを正規の任務として扱っているんだぞ。
たとえ冗談でも、銃を持っていると宣言なんかしたら…。
と思った時だった。
コウがいきなり上に向けて銃をぶっ放した。
轟音が耳に響いて何も聞こえなくなる。
「こ、コウっ…」
だが、もうコウはその場にいなかった。
人間離れした瞬発力で飛び出し、暗がりに潜んでいた二人の少年を、一動作で地面に叩き伏せる。
銃声に思わず体を震わせた次の瞬間、地面に転がっていたわけだから、少年達は何が起きたか解らなかっただろう。
時間として、2秒、かかっただろうか。
それくらい一瞬の出来事だった。
不様に転がった少年二人は、完全に無力化されたように見えた。
しかし、コウはそこでやめなかった。
懐からもう一つ銃を取り出し、撃鉄を起こして、二人を同時に狙う。
それから、薄く目を細めた。
「人質は?」
「…あ、あれ…」
少年の指が示した先には、まだ仔犬と思われるミニチュアダックスフンドが、怯えたような瞳で微かに尻尾を振っていた。
なるほど…。あれが下にいた女の子の妹って訳ね。
嘘はついてません、本当に妹のように思っている子が攫われたんです。
女の子が言うであろう言い訳が、頭の中をかすめて過ぎる。
オレはしゃがんで手を広げ、子犬を呼んだ。
仔犬は嬉しそうにオレの方に駆けよってくる。
まあ、何て言いましょうか。とりあえず人質保護完了か?
「銃は?」
だがコウの視線は、まったく少年達から外れなかった。
静かな声の中に、恐ろしいほどの迫力と威圧感が感じられる。
鈍く光る銃口も、少年達の頭をぴたりと狙って動かなかった。
最初のうちは、ただ吃驚していただけだった少年達の表情が、次第に蒼ざめてくるのが解った。
身体も小刻みに震えはじめる。
どうやら、冗談だったんです、という言葉さえも、言えなくなっているようだ。
コウが発散する空気の中に呑み込まれてしまったのだろう。
「なあ、コウ、また四月馬鹿だったんだよ」
オレはさすがにガキ共が気の毒になって、コウに声をかけた。
こういう時のコウが、いかに怖いかって、オレは組んで次の日に思い知らされたもんな。
オレが経験したコウの冷たい殺意はオレに向けられたものじゃなかったけれど、それでも充分すぎるほど怖かった。
だったら、今それが直接向けられているこいつらは、小便ちびっちゃうなんてもんじゃないだろう。
「銃は?」
だがコウの押し殺した様な声は、オレの言葉を無視して少年達に浴びせられた。
「な、な…な、無いよっ」
やっと、という感じで少年の一人が掠れた声をあげた。
「さっきは、持っていると言った」
静かすぎる声は、まるでぬめりと光る冷たいナイフを、頬に押し当てられたように響く。ほんの少し引かれただけで、ナイフはざっくりと頬を口の奥まで切り裂くだろう。
もう一人の少年が、微かに啜り泣きはじめた。
「銃を持っているなら、無条件で射殺が許可されている。たとえ子供でも考慮されない」
コウは銃口を少年達の頭に押しつけた。
ひっ…という小さな声が、口の中から漏れる。
「実際には銃を持っていなくても、持っている動作を示したり、持っていると言っただけで、射殺の対象になる」
「も、持ってません…。持っていません…」
殆ど悲鳴のように、泣きながら少年達が答えた。
「本当に?」
こくこくと地面にひっくり返ったまま、少年達の頭が動く。
両手は完全に開かれて地面につけられている。
「じゃあ何故、持っていると言った。死にたかったのか」
「冗談…だったんだよ。遊びの…つもり…だったんだ…」
「こちらには、おまえ達が遊びのつもりなのか、そうでないのかは区別が付かない」
少年達は、もう口もきけなくなっていた。
ブルブルと、ただ黙って幼児のように、首を横に振り続ける。
「コウ…なあ」
オレの言葉に、コウがやっとチラリとこちらを見た。
そして、銃身を少年達の頬に一度滑らせてから、銃口を上に向ける。
オレは、かーなーり、ホッとした。
そりゃまあ、この状態でコウが本気で撃つ事態になるとは思わなかったけど、でも万が一その必要があった場合、コウが躇うつもりは無いのも確かだったからだ。
「そのままゆっくり立て。足は開く。掌は開いたまま上げて壁に付けろ」
完全にへたれていたガキ共は、震えてなかなか立てなかった。
やっと立ちあがった所で、オレが全身をチェックする。
「何も持ってないよ、コウ」
「そうか」
コウはやっとリボルバーをホルスターに戻した。
ショットガンは仕舞えないので握ったままだが、それでも完全に銃口は下げられた。
「…こ、ここまでして…いいのかよ…」
銃が下げられた為、少しだけ気力を取り戻したのだろう。少年の一人が震える声で呟いた。
オレはふうっと息を吐いて、首を振る。
「お前、運がよかったんだぞ」
少年の瞳が、ぼんやりとオレを見返した。
「おまえ達は銃を持っていると宣言した。その時点で射殺されてた可能性もあるんだ。
持っていると一度言ったからには、最後に完全に持ってないことが証明されるまでは、警戒をとかない。だからコウのやったことは手続き通りだ。それが銃を持つって事だと、成人になる前に解ってたほうがいいぞ、お前」
少年は一瞬何か言おうと顔を上げたが、コウの顔を見ると、真っ青になって下を向いた。
コウは目を細め、静かに言った。
「二度としないほうがいい。幸運が何度もあるとは思わないことだ」
その言葉は恐ろしく重く、彼らの中に響いたようだった。
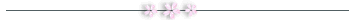
「いやあ、信じていたけどさ、でも久しぶりに吃驚したわ、オレ」
「何の話だ?」
「いや、もしかして本当に撃ったらどうしようって」
「本気だったが」
コウはまだ不機嫌な表情を崩さない。
「そりゃ、本気だったんだろうけど、でもたとえあいつらが逃げようとしたとしても、撃つ前にコウだったら取り押さえちゃうだろ?」
コウは黙ったまま答えない。
「だから撃つなんて事にはなりえない。解ってたけどさ。でもコウってば、すっげえ不機嫌だったから。確かに手続き通りだけど、荒っぽかったのも事実だし」
オレは笑いながら言った。
「まあ、これであいつら、メチャメチャ懲りたと思うよ。かなりキツかったかもしれないけど、やる時はビシッとやらなくちゃな。甘ったれて調子に乗ったガキ共にはいい薬だし、勉強にもなっただろ」
「どうして、あんな嘘がつきたいんだ…」
コウの機嫌はまったく直らなかった。
「気分悪い?」
オレは下から顔を覗き込む。
「ああ…」
「嘘は嫌いだもんな」
「嫌いだ…」
どうしようか、と白鳥は思う。
黒羽が今、誰を思い浮かべているのかは、よく解っていた。
冬馬涼一。
何もかも嘘で創られているような男。
コウの、昔の恋人。
どうしても思い出しちゃうんだよな。
本当はオレは、二度と、チラリとでもコウの頭の中に、あの男のことなんか思い浮かべて欲しくないけど。
でも仕方がない。
まあ今は、嫌な奴として思い出しているんだから、それで良しとしよう。
「本当はさ、コウ。4月1日についていい嘘は、社会の安寧秩序を乱すような嘘でない限り、って事らしいぜ。あいつらメチャ間違ってるんだよ」
「どんな嘘でも嫌いだ」
「…そうか?」
コウはチラリとこちらを見た。
「いい嘘なんてない。たとえ一時的に気分良くしてくれるものであっても、後で違うと解ったら余計に傷つく」
「言いたいことはよく解るけどね」
「香澄は違う意見を持っていそうだな」
「嘘…。嘘って言うからどうも具合がよくないんだよな。嘘をついてはいけませんって、あんまり良い言葉じゃないもんな、日本語では」
オレだってそりゃ、嘘をつかれるのは面白くない。
でも、世の中には優しい嘘があることも知ってる。
楽しい嘘があることも知ってる。
オレが大好きな刑事ドラマとかは、だって全部造りものだものな。
造りものと嘘は、ちょっと違うかもしれないけど、でも本当じゃないと解って楽しむことだって、世の中にはたくさんある。
嘘を嘘として楽しめるのは、人間だけだろ?
エイプリールフールの嘘って、本当はそういうものなんじゃないかとオレは思ったりするんだよなあ。
人間が人間の余裕みたいなものを楽しむって言うかさ…。
コウには研ぎ澄まされたような美しさがある。
ピンと張りつめてる糸のような、どこかギリギリな感じ。
オレはコウのそういう所好きだけど、でもそれは、コウには余裕が無いって事だ、とも言えるんだよな。
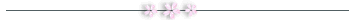
「ええと、たとえばそうだな。コウは人が死んだら無になると思っているんだろう?」
オレは言葉を探す。
「ああ」
怪訝な表情をしながら、コウがこちらを向いた。
「うん、オレも基本的にそう思ってる。死んだらお終いだって。だから生きてるうちは後悔しないように、ちゃんと生きようって」
「香澄…何の話だ?」
不愉快な気分とはまた違った、不安そうな影がチラリとコウの上を過ぎる。
ああ、ちょっとだけまずったか?
コウはこんな仕事をしているくせに、人が死ぬ話が苦手なんだった。
「うちの家族は、みんなそんな感じなんだよな。現実主義って言うかさ。だからオレもこんな風なんだろうけど。
それで、オレが子供の頃なんだけど、子猫を拾ったんだ。だけどその子猫、拾った時もう、どこか悪かったんだな。もしかしたら車にでもはねられたのかもしれない。
飼わせてくれって両親に泣いて頼んだらオッケー貰えたんだけど、でも、まもなく死んじゃったんだ」
コウは神妙な顔つきで聞いている。
オレは何となく恥ずかしくなった。
そんな真剣に聞く話じゃないんだけどな。
ガキの頃の、昔の想い出だし。
なんだかな、と思ったが、始めたからには続けるしかなかった。
「もう少し早く拾ってたら、死ななかったかもしれない。そんな事まで思ってオレは泣いたよ。ガキだったからなあ。
そしたらさ、オヤジが言ったわけ。また会いに来るよ、って。
あの子猫はちょっと出掛けただけだ。さっきうちの子になったのだから、香澄に会いに帰って来る。だから、そうしたら遊んでやれ、って。そう言ったんだ。
大嘘さぁ。おやじ、幽霊とか死後の世界とか、全然信じてないんだ。オレがガキだったから、慰めたんだな。
オレだってそのくらい解った。解ったんだけど…でも」
「…でも?」
コウの大きな瞳がオレを覗く。
「でもオレも言ったんだ。死んだ子猫に。帰って来たら、そしたら遊ぼうな、って」
「香澄…」
「来ないと思った。信じてなんかいなかった。でもオレは、その嘘が好きだったよ」
「……」
「それだけの話さ。なんだよコウ、黙るなよ。コウがオレの意見を聞いたんだろ? オレには好きな嘘があるから、コウみたいに全部の嘘が嫌いな訳じゃないって、そういう話だよ」
「うん…」
「なんだよぅ〜」
話し始めた時は、いいエピソードだと思ったんだけど、過去の話ってのはやっぱり何となく妙に恥ずかしい気がする。
「信じなかったのか?」
コウがポツリと言う。
「あ?」
「その嘘を信じなかったのか? 全然?」
「え、いやぁ。信じなかった、と思うよ。基本的には」
「少しは信じたのか」
「半々くらいかな。信じたい気持ちと、でもそんな事無いのは間違いないって気持ちと。子供としては可愛くないかな?」
オレは頭を掻いた。
ヘンだよな。
正義の味方はいるって、そういうことは思っていたくせにさ。
もっとも正義の味方は、本当にいたけど…。
そんな事思いながらコウを見ると、コウもこちらをじっと見ていた。
そして、形の良い唇を開く。
「…いや、そう思う香澄は、いいと思う」
「ああ、そう? へへへ」
気がついたらコウの機嫌はすっかり直っていた。
でかでかと顔に貼りついていた『不愉快!』の文字はすっかり消え失せている。
ううん、何が言いたいのかは、イマイチオレにも解らなくなっちゃったけど、でもコウの機嫌を直すことだけは成功したらしい。
オッケー、オッケー。
「僕には、好きな嘘はない」
「コウ」
「でも、そうだな。いい嘘はあるのだろう。きっと…」
そう言った横顔は、少しだけ寂しそうだった。
寂しそうと言うのは、もしかしたらオレの思い過ごしだったのかもしれない。
コウの表情は、あまり多くを人に語らない。
でもそう感じちゃったオレの中には、いつもの衝動が湧き上がっていた。
なんていうか、今の状況に相応しいんだかそうでないんだかよく解らないけど。
ぎゅーっと抱きしめたい。
立って歩いているこの態勢でそんな事したら、抱きしめてるじゃなくて、抱きつく、になっちゃうから、もちろんコウはどこかに座らせて。
上からぎゅーっと。
暖かい身体を抱きしめて、感じて。
でもそんな事したら、絶対チュウしたくなっちゃうけどな。
ついでに服を脱がせたくなっちゃうかも。
そこまで思って、少しだけ赤くなった。
まったく…。
オレだって、アレに関しては全然余裕がない。
抱きしめたら、速攻でベッドに突入かよ。
そうじゃないだろ?
今オレがしたかったのはさ。
腕の中で、コウを甘やかしてやりたいって、そういうことだっただろ?
せめて自分が年上だったらいいのに、と思う。
年上で大人だったら、もっと余裕を持ってさ。
大人の包容力、みたいな感じでコウを抱きしめてやれるのに。
オレの側にいる時は、コウはいつだって安心していられる。
抱きしめたら、即座にナニに直行、じゃなくてさ。
いや、その…。そうしたいのは山々だけど。
でももしオレの方が年上だったら、もう少しコウだって無意識にオレを頼りにしたりするんじゃないかなぁ、なんて思っちゃう訳よ。
まだまだオレって、世間的に見たらケツの青いガキだもんな。
コウだってオレに素直に甘える気なんか、全然なれないと思う。
うう、早く中年になりたい訳じゃないけど。
でも10年位までは、早くたてばいいのに。
そうすればオレだって、もう少しくらいは…。
  
「10年たって、30年たって、50年たったら…」
オレは無意識に、口に出して呟いていたらしい。
コウが何? と言う表情でこちらを見た。
射撃の名人は、動体視力だけでなく耳もいいのだ。
「ああ、いや、何でもない。うん…ただな、もしも50年くらいたってさ、オレ達がめでたくジジイになったら」
コウがきょとんと目を見開いた。
その表情に、オレは何となく笑ってしまう。
そうだ、今日はエイプリールフールなんだし、オレはまだ嘘をついていない。
「もういつ死んでもいいくらいジジイになって、もしオレが先に死んだら、オレ絶対コウに会いに帰ってくるよ」
コウは目を見開いたまま、オレをじっと見つめた。
「一日だってコウから離れていたくないし、他のヤツにちょっとでもコウを取られちゃうのは嫌だから」
目だけじゃなくて、コウの口もちょっと開いてしまうのが見えた。
呆れたのかもしれない。
「…香澄…。そういうのは、信じていないんだろう?」
「うん」
オレは頷く。
「それに誰かに取られるって…。僕だってその時、香澄の言うようなジジイなんだろう?」
オレは更に大きく頷き、それから腕を組んで目を瞑り、う〜ん、と唸ってみせる。
「コウのジジイは、絶対綺麗で色っぽいと思うんだよね。ご近所の老人のアイドルになっちゃってるかと。だから目を離したら誰が手を出すか、アブねえアブねえ。オレはドキドキの老後を過ごす訳。
だから、死んだ後も浮気させない為に帰ってくるんだ。オレって情熱的だなあ」
しかつめらしい顔をして、オレはうんうんと頷いた。
コウはぽかっと口を開いてそれを聞いていたが、やがて軽く吹き出した。
「僕はそんなに浮気者か。ジジイになっても?」
「ああ」
しれっとオレは言う。
「僕はジジイになっている予定なのか、香澄と一緒に?」
「もちろん当然」
「それは…」
コウの顔に微笑みが浮かんだ。
「ずいぶん楽しそうだな」
「だろ?」
「香澄が先に死ぬのは嫌だが」
「でも同時に死ぬのは、いくらなんでも無理だと思うぜ」
「じゃあ僕が先に死ぬ。年は僕の方が上だ。順番で言ったら先だろう? そして僕が香澄に会いに来よう」
オレは、楽しそうに死ぬ話をするコウを不思議な気分で見つめた。
「オレは別にモテねえと思うけど。それに浮気もしないぞ」
「じゃあ、会いに来なくてもいいのか?」
「えっ、いや。そりゃー来て欲しいよ」
「だから来る」
「でも…。コウだってそういう話、信じていないんだろう?」
「いないな。死んだら全てお終いだ。死んだ人間は会いに来たりはしない」
「だよな。オレもそう思うよ」
オレとコウは顔を見合わせて、束の間黙る。
それからプッと吹きだした。
「なんだよ、騙そうともしてないんじゃ、嘘にもならないじゃん」
オレは声をあげて笑ってしまう。
気がつくと、隣のコウも白い歯を見せて笑っていた。
うわ〜…。
声出して笑ってるぜ、あのコウが。
メチャメチャ珍しい。
冗談だって滅多に通じないのに。
「そんな風に、なれたらいいな」
「浮気者のジジイに?」
「ああ、そして香澄に怒られるんだ」
「それって楽しいわけ?」
「うん、楽しそうだ」
「…オレは、怒ってばかりで、あんまり楽しくなさそうだな」
「香澄が考えた未来だろう?」
「そりゃそうだけどさ」
「僕は…永遠も死後の世界も信じない」
少しだけ考えて、コウが静かに言った。
「でも、香澄に会いに行くよ」
不思議にきっぱりと、透明な響きを持って、コウの言葉はオレの胸に残った。

嘘でいい。
嘘でいいよ、コウ。
オレもコウも信じない。
それでも、その言葉が欲しい、と思う。
どうして人間は嘘をつくのだろう。
悪いこととされている筈なのに、なぜ人は嘘をついてしまうのだろう。
オレは思う。
多分生きていく中では、時にはささやかな嘘が必要なのだ。
優しい嘘があることを、オレは知っている。
瞞すためのものではなく、ただ言葉にして言う為だけのもの。
その人を思う心だけが言わせる
大切にしまって、とっておきたいような、綺麗な嘘。
今日オレには、好きな嘘がまた一つ増えたのだった。

「署に帰ったら、書類色々書かされるんだろうなあ…。あああ」
オレは呟きながらコウを睨んだ。
コウは肩をすくめる。
「コウのせいだぞ」
そう、ホントにコウのせいだった。
本来さっきの事件は単なる悪ふざけで四月馬鹿だったのだから、放って置いて帰ってしまえばよかったのだ。
そうすれば事件にも何にもならない。
なのにコウは、きっちり突入して発砲までした。
ということは、事の顛末から発砲の経緯まで、しっかりがっちり書類に記入して提出しなくてはならないって事だ。
警察官が書類書きに追われるのは仕事だから仕方ないとしても、本来やらなくてもいい筈だった仕事をするのは面白くない。
「発砲したのは僕だけだから、その分は僕が書く」
「そりゃ、とーぜんだよなーっ」
そんな事を言い合っていた時だった。
いきなり前から女子高生が走ってきた。
そして、コウの前にぴたりと立ち止まると、じっとコウの顔を見上げる。
オレ達二人は、きょとんとしてしまった。
オレは最初、コウのファンの女の子が走り寄ってきたと思った。
なにせコウは、砂城ではポスターなんかで顔が売れている。
そりゃ芸能人とは違うから、広く隅々にまで知られているわけではない。
それでも事件とかでコウが出てくると、写真を撮りに来る女の子までいるのだ。
さっきのガキ共だって、絶対コウの写真を何枚か撮ったに違いない。
それくらいは有名人だった。
しかし女の子はファンの行動としてはいささか奇妙なことに、黙ってコウの顔を、じっと見上げているだけだ。
「あの…」
頭の上に?マークを飛ばしながら、コウが口を開きかけたその時だった。
「えいっ!!」
気合いと共に女の子はいきなり手を伸ばすと、ぺたっ、っとコウの胸に触った。
コウは仰天して(でも表情として現れたのは、両目を少し見開いただけ。まったくコウの表情を素人が読むのは難しい)開きかけた口をぱくぱくさせた。
「きゃーーーっ♪」
女の子は叫び声を上げると、来た時と同様いきなりくるりと背中を向けて走り去っていった。
走っていく先には、友達なのであろう、何人かの少女達が彼女を待ちかまえ、同じくキャアキャアと騒いでいる。
もちろん、オレとコウは完全にあっけにとられていた。
「…い、今のナニ?」
「知らない…」
どうだったの? ねえっ。
やっぱり違う、やっぱり…だって。
賑やかな声が、風に乗って切れ切れに聞こえてくる。
「何か違うと言っている、あの女の子達。…女? 女って何の話だ」
「どっちにしてもいきなり人の胸に触っていくとは、変な行動だよな。春だから…かな?」
「それは理由になるんだろうか…」
首を捻りながら署に戻ると、いきなり広報から呼びだしがかかった。
「はい、何でしょう?」
「今ね、あっちからもこっちからも問い合わせの電話がかかってきているんですけど」
「何の話ですか?」
「いやね、どうやらどこかで嘘が流れたらしいんだけど」
「また嘘の事件ですか…」
思わずため息が出る。
さっきコウと楽しい嘘をつきあったばかりだというのに、台無しだ。
「いや、事件じゃなくてね」
「?」
そういえば呼ばれたのは広報でした。
「黒羽くんが本当は女だっていうのは事実か、っていう問い合わせなんですよ」
「はああああ?」
オレの目の中に、チカチカと星なんかが飛んでしまった。
女? コウが?
そりゃーコウは美女が裸足で逃げ出したくなるような、超美形だけどさ。
でも身長188センチもある女がいるかーっ!?
(いや、外国人ならいるか)
「だから、エイプリールフールなんだから、そんな嘘は笑ってすませてくれればいいのに。何だか問い合わせしてみたいらしいんだよね。
やっぱり黒羽くんが美人だからなのかねえ…」
広報さんはため息をついて、肩をすくめた。
「そ…、それであの女の子達、コウの胸を触っていったのか」
呆れたらいいのかどうしたらいいのか。
とりあえず再び、口が開いてしまう。
「ああ、胸触られたの。確認のために? ちゃんと男なんでしょう?」
「当たり前です!」
コウとオレは同時に叫んだ。
「それでもう、さっきから何度も問い合わせの電話がかかってくるんで、いっそのこと本人が出てくれないかなあ、と思って」
「僕が電話番をするんですか?」
「頼みますよー。本人が言うのが一番説得力あるでしょう?」
コウは眉を寄せて口を引き結んだが、それでも頷いた。
だぁ〜…。
また仕事を増やしたな、コウってば。
「今度僕でポスターを撮る時は、男だと明解に解るポスターにしましょう」
電話の前に座りながら、そんな事を提案する。
「男と解るというと、上半身裸とか?」
「いくら男でも、警察が半裸の写真使ったポスター作ったら、どこかからクレーム来るんじゃないですか〜?」
オレは思わず横から口を出した。
「そうだねえ〜。確かに」
「どうして女なんだ…」
コウは一人で、まだぶつくさ言っていた。
「まあまあ。エイプリールフールって言うのは、諸説ありますが、何でも物事を逆さまにして楽しんだ日からきている、と言うのがあるそうですよ。
男が女なんて、エイプリールフールらしい嘘じゃないですか」
広報さんはにこやかにそんな話をしてくれたが、コウは早速かかってきた電話の応対を、すでに始めていた。
やれやれ、しょーがないなー。
次に電話がかかってきたら、オレも出るか。
いえ、それは事実ではありません。今日はエイプリールフールです。
受話器に向かってコウがそんな説明をしているのが聞こえる。
やがて電話を切ったコウは、深く椅子に腰を下ろし、ため息をつきながらこう呟いた。
「嘘はそれほど嫌いじゃなくなったが、エイプリールフールは嫌いだ」
END
おまけエピソード

|