第二章 「黒羽の事情−偶然か必然か」
「黒羽さん、こんちわーっ」
「海里」
首からカメラをさげて、背の高い男がふらりと捜査一係の部屋に入ってきた。
「あっ、皆さんどーも」
調子よく特殊班のメンバーに挨拶をしていく。
「なんだ特ダネ屋、いいネタなんて無いぞ」
高田あたりにからかわれながら、海里はまっすぐに黒羽のデスクに歩いてきた。
それからキョロキョロと辺りを見回す。
「お? チビはいないの?」
「チビって…」
香澄の事か?
予想は正しかったらしく海里は嬉しそうに頷く。
「いつも隣でチョロチョロ邪魔な、寝ぐせ頭の野郎の事ですよ。いないならラッキーだぜ♪」
なんだかよく解らないが香澄と海里は、いつでもこんな風に軽口だか悪口だかをたたき合っている。
そして、2人でしょっちゅう何か色々と競い合っていた。
香澄は勝負が好きだし、年も近い。きっとライバルなのだろう。
こういうのを男友達というのかと思うと、黒羽は少しだけうらやましかった。
何を巡ってライバルなのかと考えると、実はあまり爽やかなものではなかったりするが、その大本原因の黒羽は、まるで台風の中心にいるかのようにサッパリ解っていなかった。
「チビがいないんなら、ちょっと、黒羽さん…」
海里は手招きして黒羽を外へと誘い出した。
ちょうどお昼時だったせいもあり、外に食べに行く事になる。
「何かおごるよ」
歩きながら辺りを見回す黒羽に向かって、海里は即座に首を振った。
「いや、いいです」
黒羽は微かに首を傾げる。
「香澄が、君はおごられるのが好きだと言ってたけど…」
海里は軽く舌打ちした。
「あの野郎、余計な事言いやがって。ああ、もちろん、他の奴からならそうだけど。でも黒羽さんにはおごられたくないな」
黒羽の表情が少し暗いものになる。
海里はにっこり笑って黒羽の腕をとった。
「そんな顔しねーの、黒羽さん。オレはね、黒羽さんにはおごられたくないんだ。うん。逆さ。おごりたいんだよ」
「僕に、どうして?」
「どうしてって、そりゃー、それがオレの気持ちって奴だよ」
なっ、黒羽さん。
そう言って海里は顔を寄せてきた。
海里と自分の身長はあまり変わらない。
彼の方が自分より僅かに低いが、それでも香澄とするよりずっと簡単にこういう事が出来た。
「海里…?」
気が付けばあまり見通しのよくない所にきている。
ほんの僅か建物と茂みの影に隠れれば、人に見られる事はなくなるだろう。
「オレ、砂城のこういうとこが好きだな。隠れる所、いっぱいあるだろう?」
「海里お昼は…」
海里の顔は今やごく至近距離にあった。
篁海里は香澄よりずっと『男』の匂いがした。
最初に会った時は香澄に似ていると思ったが、よく知ってくると、違いが見えてくる。
頬もそげているし、背も高い。
可愛い顔とどこかあっけらかんとした明るさを持った香澄と違って、瞳の中に暗い影があり、性的な香りもずっと濃く漂ってくる。
その海里にここまで至近距離で迫られると、少しぐらりときた。
彼の押しつけてくる体温に、落ち着かなくなる。
だが、海里は公然とホモ嫌いを名乗っていたはずだった。
黒羽は少し恥ずかしくなった。
まるで淫乱じゃないか、と思う。
男なら誰だっていいって訳ではないのだろう?
それに彼に失礼だ。
自分が海里を一瞬でもそんな対象として見てしまった事を彼に悟られたくなかった。だが、海里はそのまま黒羽の身体を放さず、まっすぐ瞳を見つめながら言った。
「黒羽さん、オレを誘ってる?」
ぎくりとした。
まるで自分の心を見透かされたみたいだった。
顔が熱くなる。
なんでいきなりこんな事を言うんだ?
それに彼の用はいったい何だというのだろう?
こういう所も香澄にはまったく似ていない。香澄はこんな風に、思わせぶりに人を振り回すような言い回しはしない。
苦手なパターンに、黒羽はますます落ち着かなくなった。
「いま一瞬妙に色っぽかったからさ」
「海里、君は…」
「オレにこうされてその気になるのって、結構嬉しいな」
「君はゲイじゃないだろう?」
単刀直入に行く事にした。策を弄しても仕方ない。
第一自分は人の心を探るのが極端に下手なのだ。
仕事でもない限り、さぐり合いと駆け引きは勘弁して欲しいと思う。
何かの間違いでそのテの用があるなら、ちゃんとはっきり言って貰いたい。
…ここまで考えて我に返った。
はっきり言って貰ってどうするって? 彼が僕と寝たいと言ったら寝るのか?
「ゲイじゃないよ。オレは女の子が好き」
黒羽はなんとなくホッとする。
だが海里は唇を舐めて言葉を続けた。
「でも、黒羽さんも好きなんだよな」
どういう意味だ?
「あのチビと旅行行くんだろ? 二人っきりか?」
「ああ、そうだがそれが何…」
「オレともどこか行かない?」
「無理だ、時間がとれない」
「無理ね、嫌じゃないんだ。オレと旅行行くってのも、悪くない?」
海里の足が自分の足を割って入ってくる。
なんだか訳が解らなくなってきた。ぐらぐらする。
「オレだって悪くないだろ? オレ黒羽さんの事好きだしさ。黒羽さんだってオレの事嫌いじゃないよな?」
彼の唇がすぐ近くにあった。
身体に手が回される。
そんなに強い力じゃないのに、彼をふりほどく事が出来ない。
黒羽は言った。
「君は僕と寝たいのか?」
…メチャクチャ直球な質問だった。

『君は僕と寝たいのか?』
なんだか前にも言ったような気がする。
よく解らなくなった頭の中に、既視感だけが広がっていく。
誰に言ったんだっけ。
過去に関係を持った男達が記憶の中を通り過ぎていく。
冬馬といた時も、冬馬に捨てられた後も、自分はたくさんの男とベッドに入った。
ベッドじゃない事も、相手が複数だった事も一度や二度じゃない。
それまでの思春期の間、ただひたすら性的な事を遠ざけて過ごしてきた反動のように男を求めた。
やりかたも男の味も、冬馬に教わった。
冬馬といた時は彼しか見えていなかったから、他のどんな男と寝ても、それが誰だかよく区別も付かなかったような気がする。
しかし彼に捨てられた後自ら求めて寝た男達の事は、一人残らずとは言わないが、かなりを記憶している。
冬馬を追うために記憶する必要があった。
自分はあれほど長い間冬馬と共にいたくせに、彼の事を何一つ知らなかったから。家族の事も、どこに住んでいるのかも、彼が何をしたかったのかも解らなかった。
もちろん調べれば通り一遍の事は解る。
しかし当たり前だが、表の世界では彼は死んでおり、死んだ人間を生者の世界だけで追う事は難しかった。
だから他の事を知るために、自分は男と寝る必要があった。
彼をほんの少しでも知っているもの。僅かな情報でもつかむために。
ベッドの上で、男達の口は軽い。
冬馬を喜ばせるために覚えた事は、他の男達も例外なく喜ばせる事が出来た。
そして、自分の中にある汚い欲望も同時に満たす。
ちょうどいい。
釣り合っているじゃないか。
誰かに欲しいと言われるのは嬉しい。
引き替えに自分の欲しいものも手に入れる。
手に入れられなくても、身体だけは満足する。
彼らの誰かに僕は言ったのだろうか?
『僕と寝たいのか?』
なんて言葉を。
「…したい」
海里は妙に赤い顔をしてぼそりと答えた。
さっきまでの人を嬲るような雰囲気は消し飛んでいる。
相変わらず自分を抱く腕に力はこもっているが、その手の先は微かに震えていた。
「どうしよう…。オレ。寝たい」
困ったように下を向き、二、三度頭を振る。
「オレ女の子が好きなんだ。ホントだぜ。裸の女見れば興奮するし。あのチビよりずっと経験豊富な筈だ。
男なんか全然好きじゃない。今だって考えただけでゾッとするぜ。
なのに畜生…」
海里は顔を真っ赤にしながら顔を上げた。
「オレ、したい。黒羽さんと寝たい」
真剣な顔だった。
その瞬間閃いた。
香澄だ!
僕は香澄に聞いたんだ。
『僕とセックスしたいんですか?』
そう聞いた。
彼はその言葉に、目を丸くして黙ったのだった。
香澄はどう見たってゲイじゃない。
もちろんコミュニケーションというものそれ自体を拒否し続けてきた自分に、はっきりした事は解らない。
だがそれでも香澄はゲイには見えなかった。
にもかかわらず僕たちは、ひっそりと抱き合い、キスを交わした。
…悪い気分じゃなかった。
でも僕は、彼がいったいどういうつもりなのか、サッパリ解らなかった。
物怖じせずに、ずかずかと自分の中に入り込んでくる彼にとまどい、うろたえる。
僕とどうしたいんだ。
どうして僕に近寄ってくるんだろう?
卑怯な理由は、他にもたくさんあったが、とにかく僕は聞いたのだ。
僕の体が欲しいのかと。
香澄は真剣な顔をして頷いた。
しっかりと僕の手を握りながら。
『オレは、黒羽さんが好きだ。だからセックスしたい。黒羽さんがいいって言うかどうか解らないけど、オレはしたい』
そして今、見上げてくる海里の瞳も同じように真剣だった。
「黒羽さんが悪いんだぜ。そんな事聞くから、オレ…」
海里の唇が自分のそれに重なった。
体が妙に熱かった。
「じ…冗談にするつもりだったのに。あのチビの邪魔をしてやろうって。それだけの…つもり、だったのに。でも…」
海里の舌が唇をなぞる。手が体をまさぐってくる。
「好きだよ。そう思ってたよ。黒羽さんだって、それは知ってただろう? なのに…寝たいかなんて。…そんな風に聞かれたら、オレ、嘘つけねえじゃねえか。そこで寝たくなんか無いって言えるほど…オレはね。
くそっ! こんな事思うなんて、自分でも信じられねえけど。でも、寝たいよオレ。黒羽さんとセックスしたい」
僕はバカだ。
黒羽は抱きしめてくる腕の中で思った。
あんな事を聞いて、そして求められたら。
僕は香澄の時だってあっさり彼と寝たんじゃないか。
「どうしよう。あんたが悪いよ、オレ…」
まずい。
海里は女相手にかなり経験豊富なようだった。
唇も、手も黒羽の感じる所に忍び込んでくる。
もちろん彼の手をねじり上げるのは簡単な事だった。
全体的な体格では負けても、黒羽は体術の天才だった。
この手をすり抜けて逆に彼を地面にねじ伏せる事くらい、2秒で出来る。
けれど、そういう問題じゃない。
あの時の香澄のように見上げてくる瞳。
僕は…。
とても彼を裏切れそうになかった。
真剣に自分を求めてくる手を振り払う事ができない。
セックスに応えるだけなら簡単だ。
だが彼は、昔自分が寝た男達とは違う。
体だけですませられる相手じゃないんだ。
そんな彼に、僕はどうしようっていうんだ。
しかし次の瞬間、海里の手が揺るんだ。
初めての男の体に戸惑ったのかもしれないし、ここが路上だという事を思い出して、手が鈍ったのかもしれない。
どちらでもいい。
黒羽にとっては幸いだった。
彼の腕から抜け出し、そのまま振り返らずに走る。
逃げるのか?
そう思ったが、今はそれしかできなかった。
海里も後を追っては来なかった。
黒羽はひたすら走って逃げた。
「香澄!」
「ななな、何?」
署に帰り、研修出張から戻ってきた香澄を捕まえ、部屋に引きずり込んで言う。
「旅行に行こう。香澄が言ってた、海外旅行」
香澄は目を丸くする。
「…どうしたのさ、いきなりずいぶん積極的だなあ。ちょっと嫌がってたくせに。もちろん、嬉しいけどさあ…」
シャツが不自然に皺になっているのを、香澄に見抜かれない事を祈った。

最初に香澄から海外旅行の話が飛びだし、それに一週間も費やそうというプランがでた時は、正直言って気が進まなかった。
黒羽は目を丸くする。
「外…に長期で旅行?」
「ただの外じゃないぜ。海外旅行! 行った事無いよな、コウ。一度行ってみたくないか? ほら、パンフ持ってきたからさ」
白鳥の瞳がちらりとこちらを見る。
なっ、なっ、二人っきりになっていい事しようぜ、とあからさまにその瞳は物語っていた。
黒羽は口の中で呟く。
「銃、は持っていけないんだよな…」
「えっ、何? 何か言った?」
「いや、別に」
人に言うと笑われる事は解っていた。
外の方が砂城よりずっと安全なんだぜ、と香澄に言われた事もある。
しかしそれでも黒羽は、銃を持っていく事ができない『外』に出る事にためらいがあった。
常に銃を携帯していないと落ち着かない。
いつ何があるか解らないような気がする。
そんな強迫観念が常につきまとっている。
香澄の近くにいると多少それは無くなるようだが、それでも心の中の深い所にそれは根を下ろし、けっして消え去る事はなかった。
『あのさあ…』
香澄の声が聞こえてくる。
『まともにやり合って、コウに勝てる奴が何人いるって言うのさ。考えてもみてよ。今年の逮捕術の試合、個人優勝者はだれ?』
『…僕だ』
『ほらみろ。何も持ってなくたってコウが一番じゃんか。畜生め』
香澄の機嫌が悪くなっていったので、黒羽は黙る。
解っていても、理屈じゃない。
自分は常に何かにたいして身構えていないと気が済まないのだ。
何が怖いの?
と一度香澄に聞かれて、初めて自分が何かを『怖がって』いる事に気が付いた。
何が怖いのだかは解らない。
恐怖は説明が難しい感情だった。
だが冷静に考えれば香澄の言うとおりだった。
殆どの人間は銃なんか常に携帯していないのだ。
だから…。
なんでもない筈だ。長期旅行くらい、なんでもない。
それに、一人じゃない。
間違いなく香澄が常に側にいてくれるだろう。
この感じなら、それこそ一日中離れないかもしれない。
一日中ベッドの上、という事もありえる。
悪い癖だとは思うが、今は目の前の問題から一時的にでも逃げ出したい気分だった。
時間が欲しい。
海里だってきっと同じだろう。
勝手な理屈をつけて自分を納得させた。
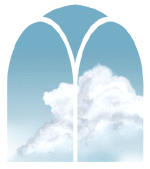
薄いカーテンから差し込む光に瞼を開けると、隣で口を開けて寝る香澄の顔が目に入った。軽く開けた唇からちらりと白い歯が見え、黒羽は微笑する。
本人が気にするから言わないが、寝ている香澄は実際の年よりずいぶん幼く見える。
身体も心も自分より遙かに『男』だという事を黒羽は知っているが、それでもこんな風に寝ている姿には、思わず笑いを誘われた。
コンドミニアム形式のここは、広々としたリビングに部屋が3つ。それにバルコニーに小さなプールまでついている。
ベッドも3つあった。
しかし香澄は当たり前のように、黒羽と同じベッドに潜り込んできた。
「手ぇ出さないって。大丈夫」
そう言いながら、それでも殆どくっつかんばかりの距離で自分の顔を覗き込む。
「へへへ。そんじゃ、お休み」
にっこり笑って言うと、香澄は目を瞑り、さっさと寝息を立て始めた。
そのあまりの素早さに、黒羽は少々呆れた。
こっちは相変わらず背中が痛くて、香澄ほど簡単には眠れそうもない。
しかし香澄の幸せそうな寝顔を見ているうちに、身体も心もリラックスしてきた。
自分は何が怖いのだか解らない。
これから先も何かに常に身構えて生きるのだろう。
けれど…。
香澄の隣では安心していていいのだ、と思う。
怖い夢も不可解な霧も、香澄の前では薄らいでいくような気がした。
ダブルより更に大きいキングサイズのベッドは、2人で寝てもかなり余裕がある。
多分、いや間違いなく香澄がそういう部屋を希望したのだろう。
彼はそんな風に何かを企画してセッティングするのが好きだった。
この部屋だって、ベッドだって、彼が色々したい事をよーく考えて選んだんだろうな、と思う。
香澄は何を考えているのだろう?
彼が何をしたいのか少々楽しみになっている自分に驚くのと同時に、この空間が自分の為にも考え抜かれた末に選ばれたのだという事にも気がつく。
大きいベッド。
他の人とあまり会わなくていいロケーション。
いつも、そうやって考えてくれている。
鈍い自分は彼の気遣いが解らない事も多いのだけれど。
香澄は思ったよりずっと大人だ…。
自分がそんな風に守られているのだ、という事実に気付く事は、少々くすぐったいが、同時にふわりとした幸せな気分ももたらした。
黒羽は手を伸ばしてその髪をなでる。
彼の寝息と自分の息を合わせる。
どんな夢を見ているのだろう。
彼と重なるようにして眠れば、同じ夢が見られるだろうか?
セックスしなくても、そんな行為にはどことなくエロティックな感覚があった。
どうやらそのまま香澄の顔を眺めながら、いつの間にか自分は眠ってしまったらしかった。
そして目覚めたそこには、また香澄の顔がある。
薄いカーテンを通した光がまともに顔に当たっているのに、まったく起きる様子もなかった。
不安など何も感じさせない、安らかな寝顔。
なんだか、ホッとした。
起きてすぐに彼の顔が見られるなんて、休みも悪くない。
黒羽は本来休まない男だった。
仕事が好きなのも事実だが、そこで自分が必要とされている事が何より大事なのだった。
仕事は逃げない。
いつでも自分が必要とされる場所。
それを短時間でも失いたくなくて、ひたすら働き続けた。
ワーカホリックと言うものなのかもしれない。
自分が優秀でいる限り、仕事は自分を拒否する事も捨て去る事もしない。
だからどんな事でもやった。
お茶くみでもポスター撮りでも、銃弾の中に飛び込んでいく事も。
休みは自分の居場所を見失う時間だった。
なのに…。
黒羽は寝息を立てる白鳥の顔を覗き込んで思う。
今の時間は暖かい。
前から香澄といると、もう少しこの時間が続けばいいと、何度も思う事があったが、今ももう少し彼の寝顔を眺めていたかった。
彼の隣にいられるなら、休みも悪くない。
この部屋も僕のために用意されたものなのだから。
だったら彼の隣が今の僕の居場所なんだろう。
いつか家を持って2人で住もう、と香澄は言っていた。
なんだか夢のような話で、黒羽にとっては火星に行く事より遠くぼんやりしたものに感じられた。
でももしかしたら、ここはそこに行きつく前の仮の場所なのかもしれなかった。
未来を信じきれない黒羽に、香澄が見せてくれた、一足早い夢の形なのかもしれなかった。
唇に、そっと指を這わす。
「…ん…」
むにゃむにゃと何か言って、僅かに眉がひそめられる。
起きてしまうだろうか?
「コウ…」
自分の名前が呼ばれた。
「なんだ?」
思わず返事を返してしまう。
夢の中でも自分と会っているのだろうか?
だったらこのままもう一度寝れば、僕も夢の中で彼に会えるのだろうか?
それはバカバカしいが、楽しい考えだった。
しかしそれを実行するより先に、香澄がこちらの世界に戻ってきた。
うっすらと目を開け、なんだかまだ半分夢の中にいるような顔で、自分を見つめる。
「あれ?」
ぼんやりとしている香澄の、その唇に、黒羽は軽くキスをした。
朝の乾いた唇。
おかえり香澄。待っていたよ。
「おはよう」
香澄は2、3度目をしばたたいた。
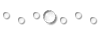  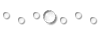
「あれ…? コウ? そうかオレ達リゾートに来たんだっけ」
香澄は目をごしごしと擦ると、にっこり笑った。
「いいなあ、目が覚めたらコウの顔があるのって」
「同じ事を考えていた」
「えっ、マジ? うわあ嬉しいなあ。旅行に来たかいがあったなあ。
こんな風に隣で寝てさあ、一緒に起きて、んでもって朝からベタベタするの。誰にも邪魔されずにさ、二人っきり」
そう言いながら手を伸ばしてくる。だが…。
「…っ、香澄」
香澄は微かに眉をひそめた。
「ううーん、まだダメ? 背中痛い?」
黒羽は黙って頷く。
がっかりする顔に、黒羽もさすがに少し考えた。
昨日は初めての経験に戸惑って香澄を邪険にしたが、ずっとこの調子というのもあまりよろしくない。
昔からうっすらと自覚はしていたが、自分は怪我の治りが驚くほど早い。
だからそれ程心配はいらないだろうとは思う。
しかしそれにしても、今夜はちょっと工夫しないと。
シーツが擦れるのはごめんだし、自分が上に乗るほうがいいよな…。
なにやら怪しげな事を、真面目な顔で検討する黒羽だった。
ホテルの食堂まで朝食を食べに行く。
朝食だけはバイキング形式でとる事になっていたので、たくさんの宿泊客が食堂に集う。
その客達の視線が、殆ど同時に吸い寄せられるように一点に集まった。
もちろんそれは黒羽高に向けられたものだった。
まったく飾り気のない白いシャツとズボン。
何も考えずにあるものを着ただけの黒羽だったが、その清楚な雰囲気が驚くほど彼の美貌を際だたせている。
部屋から一歩出るなり、たちまちたくさんの人達の注目を浴びてしまった。
わざわざ振り返って見る者。
ぽかんと見とれるもの。
指こそささないが、そこにいた人達は全て、席に着く黒羽を遠巻きに見つめて噂した。
『だれだれ? あれ』
『すごい綺麗。芸能人とか』
『王子様みたいじゃない?』
さすがに英語なら言ってる事が少しは解る。
ううーん。美人の彼女を連れ歩くのがステイタスって男の気持ちも、解らないでもないなあ。
白鳥はちらりと黒羽を見上げて満足げに頷いた。
(もっとも2人とも男だから、ゲイでもない限り、誰もオレをうらやましいとは思わないだろうけどな)
だがそれでも、みんながそろって振り返るのはかなりいい気分だった。
やっぱり新しい所にコウを連れてくるのって楽しい。
いいだろ、いいだろ。
オレのコウはすっごく綺麗だろ。
オレのなんだぞ。ぜーんぶオレの。
オレの恋人は最高だろっ?
黒羽は視線には慣れているのか、まったく何も感じていないらしい。
椅子を引いて、ふわりと腰掛ける。
それにしたって、ただ綺麗ってだけじゃなくて、妙に目立つんだよなあ。
動作がえらく綺麗だし。
それになんか、オーラみたいなのを出してる気もする。
存在感があるのか?
普通の刑事にはなれない筈だよ。
張り込みなんか絶対出来ない。
だって50メートル先からでもコウだって解っちゃうもんな。
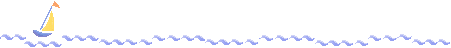
そして…。なんたることか。
言葉通り50メートル先からコウを見つけだした奴がいた。
「あれっ。嘘っ…。くろはね、さん?」
聞き覚えのすご〜くある声に嫌な予感がする。
振り向いたそこには、山盛りのパンとソーセージをトレイに盛った男が、ぽかんと口を開けて立っていた。
「た、篁 海里〜〜〜!?」
オレは素っ頓狂な声をあげてしまった。
ううむ、衆人環視の中だというのに。
「えっ!? 海里?」
コウも慌てて振り向く。
オレも驚いたが海里の方もずいぶんと吃驚したらしい。
いつもだったら腹立つくらい馴れ馴れしくコウに近寄ってくるあの男が、5秒も黙って突っ立っているなんて。
と、思った瞬間オレはとんでもないものを見てしまった。
コウが。なんだよその反応って!
コウのヤツ、海里と目があった途端、顔を赤くして下を向いたのだ。
クールビューティー。殆ど表情変わりません。
他人にはちょこっと会釈したように見えるだろうぜ。
だけどオレには解るもんね。
ちょっとコウ。どういう事?
てゆーか、何かあったわけ?
いますぐそこの校舎裏まで来て説明して貰おうじゃないか。
そんな気分がオレの中で盛り上がりかけた時、再び日本語が耳に飛び込んできた。
「あらー、偶然。海外に来てまで会えるなんて、縁があるねえ」
「おっちゃん。オカマ言葉よせって」
なんだか固まってた海里は、チッと舌打ちして、やっといつものちょっとひねた笑顔を唇に浮かべる。
だがもう一人の日本人の登場に、コウの腰がはっきりと逃げるように浮いたのが解った。
ううん…。今度の反応は仕方ないかも。
松本一彦という名前の、このおっちゃん顔の男が、コウは苦手なのだ。
時々女言葉が出る、正当派オカマのおっちゃんだが、この類い、仕事で繁華街を回ったりすれば幾らでも遭遇するタイプだし、特に珍しくもない。
どうして苦手なのか不思議に思うけど。
まあコウだってちゃんと説明は出来ないみたいだもんな。
悪い人ではないし、コウも嫌っている訳ではないようだが、世の中にはどうにも上手く対応できない人、というものが存在する。
そしてコウは、逃げようかどうしようか逡巡したみたいだが、結局立ち止まって一言絞り出した。
「海里…いったいどうして?」
……。
ええと。気のせいかもしれないけど。
その『どうして』って、妙に重くない?
黒羽は一瞬パニクりそうになった。
どうして逃げ出してきた筈の相手に、こんなところでバッタリ会うんだ?
ここは砂城じゃない。
誰も知っている人のいない所に来たはずだったのに。
よりによって海里。
腕をふりほどいて逃げ帰ってきた相手だ。
ちらりと隣を見ると、香澄がものすごく不審そうな顔をしていた。
出先でバッタリ知り合いに会ったからじゃない。あきらかに自分の不自然な反応に気付いての表情だった。
香澄はおおざっぱに出来ているくせに、黒羽の表情を読む事に関しては恐ろしく鋭い。
なんで僕はとっさに平気な顔が出来ないんだ。
自分の不器用さ加減に腹が立つ。
海里とは結局何もしていないのに。
いや、していないかどうかが問題なのではない事を、黒羽はもちろん自覚していた。
心揺れた事が問題なのだ。
あの時海里に迫られて、拒否できないかもしれない、と思ったのは事実だ。
事に及んだかどうかは結果論だった。
ろ、路上だったし…。
いや、そういう事はどうでもよくて…。
どうすればいいんだこういう場合。
思考がぐるぐる空転する。
今まで人間関係を疎かにしてきたツケが、一気に黒羽を苛んだ。
「まさか、僕の行く所を知って…」
「いやあ、吃驚した。うん。マジ奇遇ってヤツ?」
黒羽の呟く言葉を押さえ込むようにして、海里が大声を出した。
「オレ、仕事できたんだよ。嬉しいなあ。ここでも黒羽さんの顔見られちゃうなんてね。ラッキーだぜ」
「なんで海外まで来ておまえの顔見なくちゃいけないんだよ…」
黒羽が答える代わりに、横の白鳥がぶーたれる。
海里はいつも通りに相手をした。
「オレが知るかよ。オレだって黒羽さんだけに会いたかったよ。オレこそ言いたいぜ。なんでおまえが一緒にいるんだ」
「なんでって! コウはオレの恋人なんだからとーぜんだろっ!」
思いきり言い放つ。
そして次の瞬間、白鳥は自分の口をものすごい勢いで押さえた。
「……………………!!!」
し――――ん。
目立つ黒羽のせいで、さっきからもちろん衆人環視の中だ。
そこで日本語とはいえ、思いっきり男を恋人宣言。
リゾート地には日本人観光客だって結構多い。
一流ホテルスタッフには、日本語がわかる人だって大勢いる。
あまりと言えばあまりな迂闊さに、白鳥はせーだいに顔を赤くした。
海里が呆れたように口を開けて、それからニヤつく。
「押さえても出たものは戻んねえよ。屁と一緒だ」
「オレの言葉は屁かよ!」
「やめなさいよ。汚い会話だなあ…」
呆れたように隣で松本がため息をついた。
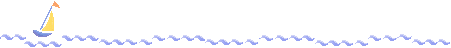
「とりあえずご飯食べようよ、ハイ座って座って」
松本は勝手に黒羽と同じテーブルにつき、海里の肩も押して、そこに座らせた。
おいおい、誰が一緒に座っていいって言ったよ。
そんな言葉が白鳥の中にちらつくが、海里ならともかく、おっさんにそのセリフを言う事はできなかった。
代わりに隣の黒羽を見上げる。
何かえらくバツが悪い。
「注目されてる?」
「さあ…」
黒羽はちらりと辺りを見回して答えた。
「ごめんコウ。オレ…」
「何で謝るんだ? 本当の事じゃないか」
「………」
黒羽は手元のオレンジジュースに口を付けながら続ける。
「香澄は僕の恋人だ。そうだろう?」
「…コウ♪」
なんか…。
なんつーか。
オレいますぐコウを抱きしめたいっ!
んでもって、チューしたい。
海里の前で見せつけるように、思いっきり濃厚なヤツを。
くそー、どうしてここは食堂なんだよー。
日本語で叫ぶだけならともかく、チューなんかしたら爆裂カミングアウト。
ああ、だけどもう、コウにこんな事言ってもらえるなら、なんだかオレ、そうしてもいい気がしてきた。
すっげえ嬉しいぞ。
『香澄は僕の恋人』
そうですっ。
そうなんです。
オレ達そういう関係なの。
コウからそう言って貰えたら、海里なんてどーでもいいっ。
だが、もちろんチューは出来なかった。
オレにだって理性はあるんだ。
…っていうか、殆どその気になって腕に触ったら、コウが顔をしかめたの。
とほほ…(ToT)
日焼けしている相手に迫るのは難しい…。
今日もダメかしらん?
海里は隣でソーセージにかぶりつきながら、少し嫌な顔をした。
ふっふっふ。まあそうだろうぜ。
おまえがホモ嫌いだ、なんて言いながら、密かにコウを狙っている事くらい解っているんだよ。なのにたった今、コウ自身からそれが難しいって思い知らされちゃった訳だもんな。
ああ、なんていい響き。
じーん…。
まさかコウ自身から、こんなにきっぱりと『恋人』って言葉が出てくるとは思ってもみませんでした。
しかも人のいる前で。
すっかりご機嫌の白鳥だったが、実は海里が『密かに』どころか、既に堂々とアプローチ済み、という事実に関しては全然解ってはいない。
まったくもって『知らぬが仏』だった。
黒羽はなんだか覚悟を決めたらしく、しれっとした顔を崩さない。
舞い上がっている白鳥と、事情を知らない(ように見える)松本を置いて、黒羽と海里、2人の間には、いま妙な緊張感が流れていた。
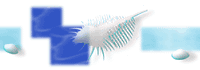
「お仕事って何ですか?」
当たり障りのない話題を黒羽が振る。
苦手な松本だが、海里に話しかけると、やぶ蛇になりそうな気がしての選択だった。
顔を向けられた松本は、黒羽のその視線に射抜かれたように、ちょっと体を震わせると、ものすごく嬉しそうににっこりと笑った。
「雑誌用の取材なんです。旅行特集みたいなもの」
「オレ、カメラマンで雇われたんだよ。つっても殆どボランティア。タダみたいなもんだけどな。知り合いだからってバイト料スズメの涙でこき使われてんの」
海里がすかさず口を挟む。
もっともその口は南国風焼きソバでいっぱいだったが。
「あらっ。心外だな。タダで海外旅行に来られたんだからいいじゃない」
「オカマ言葉やめろ」
海里に睨まれても、松本はアハハ、と笑ってまったく取り合わない。
更にちらりと妙な視線を黒羽に投げてよこした。
「やっぱり黒羽さんって、綺麗だなあ…。なんか刑事やっているのが不思議。このゴージャスなホテルにぴったり」
「あの…」
居心地が悪そうに、黒羽は椅子の上でもぞもぞする。
「ホント、ボクたち実は、このホテル一泊だけなんですよね」
「明日からは安ホテル」
海里がまた半畳入れる。
「うるさいな。こんな高いホテルに連泊出来るようなら、あんたをカメラマンに頼まないよ」
「やっぱりオレだと安くつくから連れてきたんじゃねえか」
「あの…」
黒羽が首をかしげて2人を見比べた。
「うん、このバカが話にチャチャ入れるから、全然進まないじゃない。
それでね、予算の都合上ボク達は安ホテルにしか泊まれないんだけど、そんな所の写真ばかりじゃ見栄えが悪いじゃない? だから一日だけでも無理して泊まった訳。ここのロケーションでちょっとゴージャスな写真撮っていこうって」
「ゴージャスな写真なんているのかよ。旅行特集ったって、どーせ載るのはエロ雑…」
言いかけた海里の口に、松本が思いっきりパンチをくれる。
口の中の焼きソバが宙を舞った。
白鳥が、汚ねえ! と叫んで飛び退る。
「…それで、何ですか?」
「うん。それで、出来るならね。ただ建物だけ写すってのも寂しいじゃない? もしもその写真にここにぴったりな黒羽さんが入ってくれたら、もう最高の仕事が出来そう。
どうかなあ。モデル、お願いできないかな?」
「僕は公務員だから…」
思わぬ話の成り行きに、黒羽は困った顔をした。
「公務員だから? 公務員って写真に写っちゃイケナイの?」
「公務員はバイトダメなんですよ」
白鳥が横から口を挟む。
「雑誌に載るんでしょ? そんなん見つかったら怒られちゃいますよ。それにコウの肌見れば解ると思うけど、あんまり良い状態じゃないし」
「…肌は関係ないだろう。香澄」
「いけね、頭にあったからつい」
ペロリと舌を出す。
だってこの調子じゃ今晩だってイイ事出来そうにないじゃん。
「ポスターのモデルしてるじゃない」
「あれは給料のウチです」
ううーん、と松本は考え込んだ。
「じゃあお金出さないから、で済む話じゃないよねえ。でもこれ基本的に砂城に出回る本じゃないんだけどね。通販専門だし」
「通販…?」
どんな雑誌だ? 白鳥は首を捻る。
松本がいきなり、ぽんと手を叩いた。
「そうだ、こんなのはどうかな。旅先でたまたま見つけた一人旅のストレンジャー。ちょっと寂しそうな横顔。
そのあまりの美しさに、ついシャッターを押してしまいました。スナップ写真でございます。これならモデルじゃないし、バイトでもない♪」
「一人旅じゃないですよ」
「なんだよ、そのストレンジャーってのは。おっちゃん感覚古い」
白鳥と海里の2人から突き上げられた松本だったが、まったくめげることなく黒羽の手をぎゅうっと握りしめる。
「ね? 助けると思って一枚だけ」
黒羽はギョッとしたように目を見開くと、握られた手を慌てて引こうとした。
しかし松本は、これがチャンスとばかり、しっかり握り込んで離さない。
「わ、解りました。一枚だけなら…」
「コウ!?」
吃驚して顔を見つめる白鳥に、黒羽は顔を寄せた。
「早く行って貰った方が良いだろう? 一枚だけパッと撮らせたら、それでお終いだ。ここで長々と押し問答したくない」
「はあ…。まあその。早くすませちゃえば、そりゃー、まあねえ…。だけど、大丈夫かなあー」
歯切れの悪い白鳥に、黒羽は一つ息をつくと、素早く耳元で『とっておき』を囁いた。
「早く2人だけになりたい」
「………」
白鳥は小さく口を開け、そして次の瞬間いきなり椅子を蹴って立ちあがった。
「よっしゃー。オッケーおっけーっ! ノープロブレム。ちっと雑誌に載るくらい、きっと大丈夫だよなっ。
それになんだっけ? えっと、通販専門誌なんだもんな。一枚スナップ写真が載るくらいどーってことないやっ。
さあ善は急げだ。さっさとやろうぜ。さっさとっ」
「なんだおまえ、いきなり張り切りだして…」
茫然とする海里の顔を、握りこぶしもぐぐっとさせて、全開の笑顔で見下ろす。
「んで? どこで撮るの? ホテルの中? 海の方? どこでもいいから早くしよーぜーっ!!」
さっさとやって、とっとと帰れってばさ。
「立って立って。コウもほらほらっ」
「香澄…。でもまだ朝食が。このエビ美味しいのに…」
黒羽はカニとエビフライのオレンジソース添えを名残惜しそうに見つめながら、それでも立ちあがった。
next

|