過去−dark past4−
暗闇の中で目を覚ました。
「冬馬…」
夢の続きが、自分の身体を熱くさせる。
「冬馬、どこにいる。そして何をしようとしているんだ」
黒羽は唇を噛みながら立ちあがり、そしてそのまま風呂場まで明かりもつけずに歩いていった。
もとよりよく知った自分の部屋の中ではあるが、何かにつまずくことも、どこかにぶつかることもない。
夜目が利くのだ。それもかなり。
黒羽はバスタブに入り、シャワーを捻った。
熱いお湯が全身を叩く。
悪夢を追い払うには、いい方法だった。
視力検査をすると、微妙に近眼であると測定される。
にもかかわらず、黒羽は視力で困ったことがまったく無かった。
確かに遠くのものは見づらいように思えるが、動くもの、暗闇の中のもの。
そういったものを、誰よりも先に見つけることが出来た。
ジャンクも…。
そうだ。ジャンクだって。僕は誰よりも早く気付いた。
両親を殺したジャンク。
もうあの時のことは正確に思い出すことが出来ない。
何も解らずに、呑気に扉を開けたような気もする。
だが、そうではなかったような気もした。
母親の研究室。あの地下の研究室の更に下には…。
本当はずっと気付いていたのだ。見なくても解っていた。
ジャンクがいるって。
あそこには何故かジャンクがいるんだという事を。
あれはきっと研究材料だったのだと思う。
どんなものなのか、専門に学んでは来なかった黒羽にはよく解らないが。
だが、冬馬が関わっていたことだけは確信が持てた。
そして、その全てを手に入れて、冬馬は消えた。
両親を殺し、僕を裏切り、僕を棄てた。
彼と一緒に生きていくことは、もうできなかった。
自分はそこまで強くない。
彼を殺すか、そうでなければ殺されるか。
時間はまるで、冬馬に棄てられたあの瞬間に凍り付き、そしてずっと停滞しているように思えた。
「…停滞か」
黒羽はきつく唇を噛む。
「それで? 夢の中で冬馬に犯されて、よかったのか?」
夢の中の冬馬の身体は、冷たかった。
冷たいキス。
ぞくりと震えが走る抱擁。
夢の中でも彼を殺そうと思っていた。
にもかかわらず、僕は喜んで彼を受け入れるために脚を開いていた。
「涼一…」
浅ましいくらい、身体は期待していた。
涼一に抱かれること、彼のモノに刺し貫かれること。
夢の中では、実際のセックスで常にあった嫌悪感は、どこかに消えていた。
ただ彼に抱かれる喜びで身体は熱くなる。
冷たい死人に抱かれて、僕は声をあげて達した。
「それが本音か?」
そう思うと、自分の首を絞めてやりたかった。
だが、単純な自傷行為は、黒羽には思いつきもしないことだった。
自分で自分を傷つけることは、解放には繋がらない。
他の誰かが必要だった。
セックスはその為に存在した。

どれが自分の本音なのか、考えるのは億劫だったので、「する」と決めたことに没頭する事にした。
最近あちこちで『甦ってきた死人』の噂話を耳にする。
もっとも積極的にその話を聞こうとしている黒羽の所に、その話が集まってくるのは当たり前の事だ。冷静に分析してみると、実際は噂はそれ程拡がっているわけではないようだった。
ただし、決して途切れない。
忘れた頃になって、ふっと新しい話が出てくる。
そう、これは間違いなく冬馬の足跡だった。
直感が、そう告げていた。
冬馬が消えて最初の半年くらいは、自分は殆ど使い物にならなかった。
上手く動くことすら出来なかった。
リハビリと、仕事で求められることのみに没頭する。
次の一年は、冬馬の情報を集めて歩いた。
彼が何者だったのか。
どんな足どりを残していたのか。
不思議と冬馬はぷっつりと姿を消していた。
まるで本当に死んでしまったかのように動かず、息を潜めていた。
一時期は、実は本当に死んでしまったのではないだろうか、という迷いが自分の中にも生じた。
そんな筈はない。
そんな筈はなかった。
彼はあの段階で、確かに何かを企んでいたのだ。
すぐには動けない事情があるのかもしれない、と思う。
冬馬は本来なら時間を無駄にしないタイプだからだ。
密やかに水面下で何かを進めている可能性もあるが、黒羽は冬馬のジャンクに2発ショットガンを撃ち込んでいた。
あの大きさのジャンクは、2発程度では崩れない。
しかし、無事でもいないはずだ。
もしも自分があのジャンクを傷つけたことが、彼の計画を遅らせている原因の一つなのだとしたら、少なくとも冬馬に一太刀はくれてやることができたのだと思う。
冬馬が何をしようとしていたのか、本当のところは解らない。
しかし彼の望みは、彼の声の響きとともに、ハッキリと耳の底に残っている。
『永遠に生きていたくないか?』
永遠を求めているロマンチックな冬馬。
いつでも夢の話をとりとめもなくベッドで囁いた冬馬。
そのどれもを僕は聞き流してきたけれど。
あれは全部本気だったのだ。
そして彼には、夢を夢のまま終わらせないだけの、実行力と権力があった。
永遠を、手に入れたのか? 冬馬。
それともまだ途中か。
街に現れる死人の噂はなんだ。
それは、ジャンクなのだろうか?
ジャンクならば、たとえそれが『人』の形をしていたとしても、撃たなくてはならないだろう。
何故なら自分は、ジャンクを撃つために銃を握ったのだから。
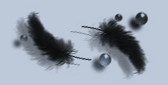
「んっ…うぅん…。あっ」
男の上に跨がって、腰を動かす。
下から突き上げてくるモノが、黒羽の中を擦りあげる。
「ああぁっ…」
思わず大きな声が出た。
「りょういち…」
名前を呼ぶ。
ひどく倒錯した気分。
自分の中を抉っている男の名前は、亮一といった。
もちろんこちらは名前など明かさない。
それは黒羽と寝るための『誓約』であり『条件』だった。
「いい…。すごくいい。亮一。あんたの…いい。あぁっ」
名前を呼ぶたびに、まるでそれが呪文でもあるかのように、気持ちは過去へと帰っていく。
気持ちいい。
身体中が熱くなっていく。
好きだった。愛していたと、そう思っていた。
愛するという事がどんなことなのか、あの時そう思いこんでいたのも何もかも嘘だったのか、黒羽には解らなくなっていた。
自分にとって信じられる愛とは、もう両親がくれた愛しかなかった。
育てて、守りたい。
これは、間違いなく愛だろう。
なのに僕は、決して育まない性しか持たない。
最初から裏切り者だ。
恋人への愛と、親子の愛は違うと解っている。
けれど、見つけられない。
涼一への気持ちが愛だと思っていたが、それはもう解らなくなってしまった。
ああ、そんな事はどうでもいい。
亮一という名の知らない男にキスをせがむ。
セックスの最中のキスが、僕は好きだった。
こんなセックスをするようになってからは、あまりしたことがなかった。
けれど今は、彼の名前を呼びながらキスをする。
唇を舐めて、舌を絡ませる。
りょういち、すごくいいよ。
もう一度逢えたら、どうすればいいんだろうと、僕はずっと思っていた。
時間は止まっている。
過去には帰れないし、未来はぶつりと途切れている。
『僕を殺して』
あの瞬間そう思った。
そしてそのまま時間は凍り付いている。
どうして僕を殺さないんだ、りょういち。
あんたがしないなら、あんたに教えて貰った事を、僕の方から返す。
ここに銃はないから、この腕と指で、あんたに教えて貰った方法で。
ちゃんとできたなら、僕を見て褒めてくれ、涼一。
よくやった、コウ。
教えた通りに上手くできたと、そう言ってくれるだろう…?

はっ、と我に返った。
鼓動が恐ろしく早くなり、同時に頭から冷たい水を浴びせられたように身体中が凍り付く。
男が自分の下で吐いていた。
何をした?
殺そうと思った?
この男を、冬馬だと思って?
ついに自分が狂ったのかと、黒羽はぞっとした。
名前の響き以外、どこも似ていないこの男に、無意識に殺意を向けた。
僕は壊れかけているのか。
僕はいま何を考えていた。
彼は違う、彼は、彼は…。
男は苦しそうに喘ぎながら、奇妙な瞳で黒羽を見つめた。
何か言おうとしたが、声が上手く出ないようだった。
だが、命に別状はなさそうだった。自分はやりかけたが、やりすぎるところまでは行かなかったのだ。
安心と困惑が一気に押し寄せてくる。
そしてそのまま、何も言わず黒羽は逃げた。
自分自身が恐ろしかった。
冷静に彼を捜そうとする自分と、衝動に身を任せようとする自分。
二人の自分が混沌の中でもがき続けている。
どこかおかしいんじゃないか?
あの時から僕は、だんだん狂ってきているのではないか。
恐怖と罪悪感が胸に拡がる。
僕の立っている場所はどこだ。
崖淵にいたと思いこんでいたが、実はもう胸の中にある、暗い穴に落ちてしまったのではないか。
怖くて怖くて、仕方がなった。
黒羽はしばらくの間、仕事のみに没頭した。
罪悪感を奉仕する事で少しでも薄められたら、とそう思った。
セックスは自分を罰するためにあった。
仕事は罪を償うためにあった。
黒羽の心に意識されることはなかったが、それは深く胸の中に打ち込まれて、容易には抜けない楔のような思いだった。

そして
黒羽は再びあの男に会った。
上ではなく、アンダーで。
犯罪捜査の最中に、汚い路地裏で薄汚れて転がっている男を、偶然黒羽は見つけた。
見た瞬間に解った。
髪と髭が伸び頬がそげて、容貌は変わっていたが、自分を見上げる瞳は確かに彼だった。
「りょういち…」
思わず呟く。
男は路上にへたり込んだまま、しばらく不思議そうに黒羽の顔を見上げていたが、名前を呼ばれると目を見開き、力無く微笑んだ。
黒羽が誰なのか思い出したように見えた。
「よかった…」
上手く動かないらしい口から、ガサガサした聞き取りにくい声が漏れてくる。
「殺…して、くれ」
黒羽は膝を折って男の顔を正面から見つめた。
…もう、長くない。
男は息をしていなかった。
触れなくても解る。身体は氷のように冷たいだろう。
それでもまだ生きているかのように唇を開き、言葉を発する。
だが、長くない。
彼はもうすぐ崩れる。
壊れたジャンクのように。
どうしてそんな事が解るのか、それは不思議な感覚だった。
だが生き物は、死に近いが故に死を感じる直感力があるのかもしれないと思う。
この男はもう死んでいるけれど、それでも解る。
彼は、まもなく彼ではなくなるのだ。
「殺して…くれ」
もう一度、最後の望みのように男は呟いた。
瞳は黒羽の顔ではなく、左手に握られているショットガンに据えられている。
「あの時みたいに…。俺を、殺して」
次第に小さくなっていく声に、黒羽は更に身体を男に近づける。
「あんた…、帰ってしまったから…。話が、できなかった」
「その時持ってきた話が、今の姿なのか?」
男は小さく頷く。硬直しかけた身体は、不自然にぎしりと動いた。
「もう一度…こんどこそ。お願い…だ」
「では、話を聞かせてくれ」
黒羽は目を瞑り、軽く息を吐くと、男の身体を抱きしめた。
ぞくりと震えが走る、冷たい抱擁。
脇腹から心臓に向けて、銃口を押し当てる。
「冬馬涼一を知ってる?」
男は黒羽の耳元で、一言二言囁いた。
「さよなら、亮一」
黒羽の言葉に、男はうっすらと微笑むと瞳を閉じる。
次の瞬間、彼の心臓に向かって散弾が撃ち込まれた。
男の身体は弾けて消えた。
本来は存在し得ないものが、闇の世界に帰ったように。
張りつめていたその瞬間を、黒羽の銃弾はただ破っただけ。
そんな風に、男の身体は崩れて溶け消えていった。
「黒羽さん?」
銃声に驚いたように、パートナーが駆けつけてきた。
彼は口を開きかけたが、薄暗がりの中に膝をつく黒羽の姿に、何故か一瞬ギョッとしたように口をつぐんだ。
黒羽はゆっくりと彼を見上げる。
「すみません、辻さん」
その声は穏やかだったが、人間らしい感情は何も籠っていないように響いた。
「ジャンクがいました」
「ええっ?」
「小さいものでした。一瞬で弾けて、終わりです」
「そ、そうか。確かにここは穴が近いから。注意した方がいいかもしれない」
パートナーは頷いて、注意深く拳銃を抜いた。
ジャンクを撃つために、自分は銃を手に持った。
冬馬、お前がジャンクなら、僕は誰よりも早くお前を見つける。
暗闇の中でも、はっきりと解るだろう。
ここに、アンダーに。
この世界のどこかにお前はいる。
黒羽は地の底を透かして見るかのように、黙って足元を見つめた。
END

|