苦い水
「会ってくれますか?」
電話の向こうの声はそう言った。
黒羽は目を瞑り、記憶の中からその声を探しだす。
「はい、篁さん」
名前を呼んだら、電話の向こうの相手が、何故か震えたような、そんな気がした。
篁 海里からいきなり電話がかかってきた。
もちろん彼のことは覚えていた。
爆破事件のただ一人の生き残り。自分が彼を引きずって爆発から遠ざけた。
時間が経過しても忘れるわけはない。
しかし、事件自体は既にほとんど収束していた。
8人もの人間が死んだ大事件ではあったが、犯人は死亡しているうえ、既に四ヶ月の時が流れていた。
世間の移り変わりは早い。
連続爆破事件は、とっくに終わった出来事という扱いになりつつあった。
だが事件の当事者は、そうはいかないだろうと思う。
篁 海里はその当事者だった。
あの事件で、心と身体に大きな傷を負った。
たとえ十年経っても、忘れられないに違いない。
自分が決して両親の死を忘れることが出来ないように。
彼には事件直後にただ一度会ったきりだった。
とりあえず名刺を渡し、何かあったら連絡を、と言い置いてきた。
しかしそれきり彼に会うことはなかった。
生きていれば多くの人と出会い、すれ違う。すれ違ったまま一生会わない人間もいる。
だから、彼のことは忘れたことはないが、気にもしていなかった。
なのに今、どうしていきなり電話をかけてきたのだろう。
電話の向こうの声は、妙にくぐもっていた。感情を押し殺したような、何かを心に重く抱えているような、そんな声。
事件に関して何か思い出したことがあるのかもしれなかった。
世間的には終わった事件だが、思い出したことがあったらなんでも言ってくれと言ったのは自分だ。
あれは冬馬が仕掛けた事件だった。
どんな些細なことも聞いておきたいし、知りたい。
たとえ無駄足だったとしても、それでもいい。事件に関して彼の話を聞くことができるのは自分だけなのだから。
篁 海里は事件に関して話すことを封じられた。
それはひどく苦しいことだったに違いない。
彼にそれを強制したのは警察なのだから、どんな話でも聞く義務があるだろう。
黒羽は腕の時計を見る。
仕事はとっくに終わり、そろそろ針は八時を指そうとしていた。
指定された場所まで、車で行けばすぐだ。
少々問題があるとすれば、黒羽一人で来てくれ、と要求されたことだった。
事件の話となれば、香澄は絶対に来たいと言い出すだろう。
正直に相手の要望を話してもいいのだが、まだ向こうの話がどんなものか解らない以上、あまり大げさにはしたくなかった。
「香澄…今日は」
言いかけた黒羽に、白鳥はひどくせわしない様子で返事を返してきた。
「ごめん。コウ、先に帰って。桜庭さんに怒られちゃったよ。デスクワーク溜めるなって。経理からも請求伝票はどうしたって言われちゃってさあ。まったくあれもこれも一気に出来るかってーの」
少しずつやっていけば、一気にやらなくてもいいだろう、という言葉を、黒羽は苦笑と共に呑み込んだ。
警察の書類書きは自筆が基本だ。他人が手伝うことは出来ない。
今の状況には、大変都合が良かった。
「解った。僕は外で食事してくるから、少し遅くなると思う」
うんともふんともつかない返事を口から漏らしながら、白鳥は机から眼を離さない。
黒羽は彼の邪魔にならないように、そっと部屋を出ていった。

指定された場所に、篁 海里はボーッと立っていた。
腕の下には松葉杖が見える。
かなり近くに行くまで彼はこちらに気付かず、声をかけた瞬間まっすぐ上に飛び上がった。
「わっ! ああ。く、黒羽さん」
「すみません、お待たせしましたか?」
篁 海里はキョロキョロと視線を動かし、恐ろしく落ち着かない様子だった。
「一人ですよ」
黒羽が言うと、彼の顔は真っ赤に染まった。
黒羽は少し不思議な気分になった。
こんなに感情豊かな男だっただろうか。
もっとも彼と会ったのはたったの二回。
しかも最初は事故現場で次は病院だったわけだから、普段の彼がどんな男かは、まったく知らなかった。
「待ったって言うか、オレの部屋、すぐ上なんです」
「上?」
海里はすぐそばのアパートに向かって、顎をしゃくった。
二階建ての古いアパート。たぶん彼の部屋は二階にあるのだろう。
「ホテルとか店とか、洒落たところで会うような金はないから、オレ」
「どこでもかまいませんよ」
「そう? じゃ、部屋に上がってくれ。立ち話という訳にはいかないから。何もないけどな」
ぶっきらぼうに言いきると、海里はくるりと背を向けて、アパートの階段を上がっていった。
黒羽も後に続く。
海里の杖をついての歩行に、一瞬手を貸そうと思った黒羽だったが、器用に昇っていく姿に、改めて自分が助けた男を見つめた。
彼は香澄と同じくらいの年の筈だ、と思う。
横になった姿しか見ていなかったが、こうしてみると背はかなり高い。
体格だけで言うなら、香澄より大きかった。
しかし、後ろ姿は妙に子供っぽい、と思う。
若者特有の虚勢のようなものが、彼の背中から滲み出て見えた。

部屋は思ったより片付いていた。
というよりものが少ないのだろう。
かろうじてテレビは置いてあるが、あとはローテーブルと部屋の隅に寝具が一組積んであるだけだ。
「茶も出せないんで」
そう言って海里は缶コーヒーをテーブルに置いた。
「座布団もないけど、適当に座って」
黒羽は言われるまま畳の上に腰を下ろす。テーブルをはさんで、海里が真正面に座った。
だが彼は黒羽と視線を合わせようとせず、落ち着かない様子で缶コーヒーを開けた。
「お久しぶりです。身体は大丈夫ですか?」
「あ…うん」
コーヒーを口に含んだまま、海里は曖昧に頷く。
それから視線を、立て掛けた松葉杖に向けた。
「もう、かなり大丈夫。杖はついてるけど、ほとんど補助みたいなものだから。医者は、そのうち杖なしで普通に歩けるようになるって言ってたよ」
「そうですか。それはよかった。僕も嬉しいです」
「黒羽さんが、オレが歩けるようになって嬉しい?」
「はい」
「どうして?」
「どうしてと言われても。怪我が治るのは嬉しいでしょう?」
「オレはね。でもホラ、黒羽さんには別に関係ないって言うか…」
「関係、ないですか」
「…あっ。そういう意味じゃなくて。人事って言うか、いや違うって。えーとえーと、オレはバカか」
海里は再び顔を真っ赤にしながら、ガリガリと頭を掻いた。
黒羽は可笑しくなった。口元が綻んでくるのが解る。
「あなたが生きていて、僕は嬉しいですよ。怪我が治るのは生きているという事でしょう?」
「オレが生きていて、嬉しい? 全くの他人でも?」
「他人ですけど、僕の目の前で怪我をした。そういうのも一種の関わりでしょう。どんな形でも関わった人間が死ぬのはやりきれないし、生きていてくれて、本当に嬉しい」
海里は顔を赤くしたまま、下を向いていた。
「うん…。あの場にオレがいたことを知っているのは、黒羽さんだけなんだよな…」
言葉を噛みしめるように海里は呟いたが、次の瞬間ハッとしたように顔をあげた。
「うわっ、オレッて馬鹿。黒羽さん、助けてくれてありがとうございました。ずっと言わなくちゃって思ってたんだ。助けてもらったお礼。なのになんか、実際に会ったら舞い上がっちゃって。しょーがねえな、オレ。
ええとその、本当にありがとうございました。おかげでオレ。生きてますっ!」
海里は初めてまっすぐに黒羽と視線を合わせ、それから深々と頭を下げた。
黒羽は黙ってその言葉を受け入れた。
自分はこんな風に礼を言われるような立派な人間ではない。誰かを一人助けたとしても、その何倍も傷つけている。
だが、もちろんそんな事を海里に言うつもりはなかった。
彼が礼を言いたいのだ。だからただ黙って受け入れよう。
「もう、頭を上げてください。今日はそのお話で僕を呼ばれたんですか?」
黒羽の言葉に、海里は再び体を硬くした。
どうやら他にも用件はあるらしい。
しかし何故か解らないが、それを切り出しにくいようだった。
黒羽は自分から水を向けてみることにした。

「あの事件のことで、何か思い出されたことがあるんですか?」
「あ……」
海里は顔をあげる。
「あのさ」
どこから切り出そうか、彼は悩んでいるように見えた。
「どんなことでも話すだけで気楽になることはあります。捜査に関係ないとか、もしも気にしているのなら、僕はかまいませんから、何でも話してください」
「ああ…捜査。捜査ね。犯人は捕まったんだよな。といっても死んでからだけど」
「はい、残念なことに」
「べ、別に警察を責めているワケじゃないぜ。とりあえずあいつが犯人なら、もう被害者は出ないって事だもんな。オレは、運がよかったんだ。黒羽さんが、偶然いてくれたから」
海里は小さく唇を噛んで、目の前の黒羽にも聞こえないほど小さな声で呟いた。
「いたのが黒羽さんで、本当によかった…」
「なんです?」
黒羽は海里の言葉を聞き取ろうと、顔を近づける。
再び海里の顔に朱が散った。
「あの、あのさ。新聞記事とかたくさん読んだんだけど。オレが入り口ですれ違ったのって、結局犯人だったんだろ? 兄弟の、弟の方?」
「そうです」
「オレ、そいつとすれ違った時。病院で言ったと思うんだけど、ぶつかったんだよ、そいつの身体に。寝不足でふらついて思わずしがみついちゃった感じだったけど」
海里はチラリと黒羽の顔を見つめた。さっきよりずっと近い位置に顔がある。
黒羽は黙って話の続きを待っていた。
「あの男は、いったい何なんだ?」
「何…と言うのは?」
「黒羽さん、誤魔化すのはやめてほしい」
黒羽の眼鏡の奥の瞳に、フッと光が灯った。優しく緩みかけていた口元がまっすぐ結ばれる。
「あれ、人間じゃないんだろう?」
質問の形を取ってはいたが、海里の瞳は確信に満ちていた。
黒羽は大きく目を見開く。
その通りだ。少なくとも生きている人間じゃない。彼も気付いたのだ。体温の無い男に。
多分、身体に触ったから解ったのだろう。
ただすれ違っただけでは、ほとんどの人間は多少おかしいくらいにしか思わない。いや、もしかしたら篁 海里は、非常に鋭い感覚の持ち主なのかもしれなかった。
だが、自分はどう応えればいいだろう。
この件に関しては、警察は関係がなかった。仕事で対応する事はできない。
しかし自らのプライベートに彼を巻きこむわけにもいかなかった。
黒羽は注意して言葉を選ぶ。
「それを何故、僕に聞くんですか?」
「ずっと、考えていたんだ。あの男は変だったって。冷たい、死体みたいな身体。ぞっとして、忘れられなかった。なのに、警察は別に関心がないみたいだった。だからオレは調べたんだ。個人的に色々と」
黒羽の心の中に、不安が湧き上がってきた。
まずい。よく解らないまま、彼は泥の中に踏み込もうとしている。
「…それを、どうして今になって僕に?」
不安が声に出ないように、黒羽は低く呟いたが、海里は更に深いところにいきなり切り込んできた。
「だって黒羽さんが知りたいのは、その情報だろう? だからオレに名刺をくれた。違うのか」
今度こそ黒羽は、ぎくりと身体を震わせた。
僕はどこかでドジったか。
あからさまに彼に、自らの意図を悟られるような態度を取ってしまったのだろうか。
海里はしばらく黒羽の様子を窺っていたが、やがて軽くため息をついた。
「黒羽さんって、表情無いな。何考えてんだか、よく解らないや。まあいい。一応オレ、黒羽さんに言っておこうと思って。あの男が何者なのか、オレは何に巻きこまれたのか、オレは調べるつもりだ。
警察はその事に関してオレの敵かもしれないけど、黒羽さんはオレの命の恩人だから…」
「だから、僕に話した? 自分が何をやろうとしているのか?」
海里は頷いた。
「ああ、オレは調べるつもりだ色々と。個人で出来ることは少ないけど、オレにはオレのルートがある。黒羽さんが情報が欲しいなら、やるよ」
海里の言葉に、黒羽はスッと眼を細めた。
「あなたが、僕が欲しがるどんな情報を持っていると?」
途端に海里の顔は真っ赤になった。
唇を軽く噛み、何かに苛ついているように膝を揺らす。
海里は自分に表情がないと言った。
だから何を考えているのか解らないと。
目の前の男はおそろしく表情豊かだった。
赤くなったり青くなったり、慌てたり逡巡していたりする。
だが、何を考えているのかは解らなかった。
解るのは、彼が何かを隠しているということだけだった。
それが彼の態度を曖昧なものにしているのは間違いがなかった。
彼は何を隠しているのだろう。
まさか…。
彼は持っているのだろうか。
自分が求め続けた男の、何らかの情報を。
あの事件自体ではなく、体温の無い男を調べていったのなら、探っていくうちにどこかで彼の影に出会った可能性はある。
事件の被害者に会うのだと思っていた。
話を聞くことによって、自分が助けた男の、何らかの力になればいいと思っていた。
しかし…。
ゆるやかに黒羽の心の中で何かが切り替わっていく。
彼が僕に必要な情報を知っているなら、それが欲しい。
黒羽はもう一度、篁 海里をまっすぐに見つめて言った。
「篁さん、あなたはどこまで、何を知っているんです?」
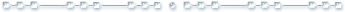
篁 海里は、どうしようもないくらい緊張していた。
手のひらには汗がじっとり滲んでいるのに、口の中はカラカラに乾いている。
舌が上手く動かない。
だって、黒羽さんと部屋の中で向かい合って座ってるんだぜ。
心臓だってドキドキして、鼓動が外にまで響いて聞こえちゃうんじゃないかと心配になるくらいだ。
久しぶりにちゃんと顔を合わせたけど、やっぱりすげえ綺麗だ、と思う。
オレの部屋に座っているなんて嘘みたいだ。
しかも…二人きり。
黒羽さんは大きな瞳で、じっとこっちを見ている。
オレだけを映している瞳。
オレの名前を形づくる唇に、キスしたい…。
海里は完全に混乱していた。
とにかく黒羽 高と話したい。正直な気持ちは、ただそれだけだった。
自分を意識して欲しい。自分がやることを知っておいて欲しい。
ただ、それをどんな風に話したらいいのかは、会う直前になっても結局決まらなかった。
そして、会ったら会ったで話さなくてはいけないことと、黒羽への想いと欲望がごちゃごちゃになって収拾がつかない状態になっている。
どうする? 何からどう話す?
好きな人の前でカッコつけたい気持ちが、もちろん多少はあった。
だが結局、不様と言い捨ててしまえるくらい、あちこちにぶつかりながらの会話になってしまった。
しかし黒羽さんは、いま真剣な顔をしてこちらを見ていた。
息がかかるくらい近くに、彼がいる。
そして、オレの話に興味を持っている。
頬に血が昇るのが解った。
「篁さん、あなたはどこまで、何を知っているんです?」
どこまで何を知っているかって?
黒羽さんが追いかけてる情報を?
全然知らない。ホントのこと言うと、黒羽さんの後ろで立ち聞きした情報の欠片がすべてだ。
もしかしてこれから、翔子から情報が手に入る可能性だけはあるけど。
それだって不確定だし、今のオレは、全くの空手だ。
どうする?
もちろん立ち聞きしましたなんて言えない。
でも、何も知らないと思われて興味を無くされてしまうのも厭だった。
どんな形でも、黒羽さんに注目してもらわなくては、ここまで呼び出した意味がない。
仕方なく、オレは切り札を出した。
「冬馬涼一って男が、関係してるんだろ?」
黒羽は表情をまったく変えず、ただ瞬いた。
しかし次に出てきた言葉には緊張が感じられた。
「その名前…、どこで?」
「どこだかは教えられない。けど、でも、誰だかは知ってる。冬馬グループの関係者だ。そいつが、関わってるんだろう? あの事件に…」
「彼の何をご存じなんですか? 篁さん」
黒羽の眼には、あきらかに違う光が宿りはじめていた。
「情報との引き替えに、何か交換条件があるなら、違法でない限りお応えしたいと思います」
「交換条件――」
海里の心臓は一泊跳ね上がる。
こ、交換条件ってなんだよ。いきなり。もしもオレが黒羽さんにキスしたいとか言ったら、それも呑むのか?
海里はごくりと喉を鳴らした。

「じ…じゃあさ…。黒羽さん。まずその、敬語やめてくれよ。篁さんってのも無しだ。名字で呼ばれるの嫌いだから。海里でいい」
「えっ?」
黒羽は虚をつかれたという表情をする。
しかしすぐに、自嘲を含んだような口調で呟いた。
「同じ事を…前にも言われた。僕の敬語は、どこかマズイのかな」
「マズイわけじゃないけど…」
オレはあんたと親しく話したいんだ。
そんな他人行儀な敬語じゃなくて、隣に立っているのが自然なくらい親しく。
そう思った瞬間、頭の中を過ぎったのは別の男の姿だった。
そうだ。いま、隣に立っているのはオレじゃない。
胸の中に、黒い靄ががせり上がるのが解った。
「前にも同じ事を言われたって、誰から? ……あの、男からか?」
「男?」
海里が何を思い浮かべたか解らない黒羽は、眉を寄せて怪訝な表情をした。
仕方なく海里は口にしたくない男の名前を出す。
「…かすみ、とかいう」
「ああ、香澄。そう。香澄に言われた。海里さん、僕のパートナーを知っているんですか?」
また一瞬敬語に戻ってしまい、それに気付いて黒羽はくすりと笑った。
その顔がおそろしく魅力的で、海里は強烈な嫉妬心を感じた。
黒羽さんをこんな風に笑わせる事のできる男。
黒羽さんのパートナー。
畜生、パートナーってなんだよ。恋人同士って、暗に言ってんのか?
「し、知ってるさっ。見たことあるからな。あんたたちが…その」
「僕たちが?」
黒羽はわずかに眉を上げる。
「あんたたち、キス! してただろっ?」
「……ああ」
黒羽は眼を細めた。しかしそれ以上表情は動かなかった。
もっと動揺するかと思った海里は、アテが外れて頭に血が昇る。
畜生、また混乱かかってる、オレ。
もっとクールに、黒羽さんに自分をアピールするつもりだっただろ?
こんな流れにする予定じゃなかったのに。
なのに畜生、あんな男の名前を出したせいで…。
だがもう、やめる事が出来なかった。
「否定、しないのか?」
「できないから」
これもあっさりと返される。どこまでも冷静な声が、海里を苛だたせた。
「へえ。警察にゲイがね。まあゲイは違法じゃないけどさ」
「海里さん、確かに僕はゲイだ。だからあなたが言いふらしたいなら、かまわない。しかし香澄のことは容赦して欲しい。彼はゲイじゃない」
「でも、あんたと寝てるんだろ?」
庇うような言葉にカッとなって、海里は余計なことまで口走ってしまった。
ここまで言うつもりはなかったのに、と後悔したが、黒羽は肯定も否定もせず、指を顎に当てて少しの間、何かを考えていた。
それからチラリと海里の顔を見上げると、スッと立ちあがる。
海里は狼狽した。
まずい。やっぱり言いすぎた。
なんでケンカを売るような流れにしてんだ、オレ。
もしかしてこのまま帰っちゃうのか? 黒羽さん。
でも謝るにしても、なんて謝ればいいんだろう。
しかし黒羽は帰る代わりに、ジャケットを脱いで海里の隣に腰を下ろした。
「えっ!? く…黒羽さ…」
たちまち海里はパニックに落ちいった。
だって、この至近距離。友達だってこんな近くには座らない。
薄いシャツを通して体温を感じる。
黒羽さん、いったい何を……。

黒羽はキスが出来るほど近い位置に顔を寄せて、囁くように言った。
「海里…。君は僕と寝たくはないか?」
「えっ。ええっ…?」
「確かに僕は香澄と寝ている。だが他にも多くの男たちとも寝ている。僕は、僕と寝たいとそう言ってきた男とは、誰とでも寝るんだ。特に冬馬涼一の情報を持っている男だったら、僕は喜んで寝る」
耳に息がかかり、手のひらが、海里の膝に這い上がってきた。
その感触に、背中がぞくりとする。
「く…黒羽…さん」
「海里、君は何かを知ってるんだろう? 僕は君の持っている情報が欲しい。代わりに僕が欲しいなら、いくらでも、海里の好きなように…」
「黒羽さん、オレは…」
「海里が僕に、こんな風に突っかかってくるのは、僕に興味があるからなんだろう?」
「そっ…そんな…こと」
「僕と、キスしたくないか?」
答えを待たずに、黒羽はすうっと顔を近づけてきた。
唇が海里のそれに重なり、何が何だか解らないうちに唇を吸われ、舌を差し込まれた。
頭がクラクラする。
鼓動で心臓が破れてしまいそうだ。
キスくらい何度もしたことがあるのに。
でも、黒羽さんの柔らかい唇。
探るように動く舌。
膝の上に置かれた指が、腿に這い上がってくる。
「黒羽さん、オレ……。黒羽さ…」
海里は熱くせりあがってくる衝動のまま、黒羽を押し倒していた。
まったく抵抗なく押し倒された身体の上から被さって、今度は自分の方から唇を重ねる。
黒羽は長い睫毛を伏せて、海里の背に腕を回した。
「ん……」
すごい、と思う。
オレ今、黒羽さんとキスしてる。
こんな風に身体重ねて。
妄想の中だって、こんないきなりの展開はなかった。
夢中で唇をむさぼる。
甘い。いい匂いがする。
黒羽さんの白い肌に、うっすらと血の色が昇り、だんだん熱くなっていく。
初めて見た瞬間から、黒羽さんが好きだった。
こんな風になりたいって、ずっと思ってた。
夢中でキスをして、唇を離すと、綺麗な顔がすぐ近くでこちらを見上げていた。
オレは、それこそバカみたいに、ボーッと見とれてしまった。
今その唇にキスしたんだよな?
ホントにしたんだよな?
「海里、ここでする? それとも、場所を変える?」
黒羽さんが囁く。
する? するって何を?
「セックス。僕とするんだろう?」
黒羽さんのピンクの舌が、すうっと唇を舐めていく。
ドキリとした。
セックス…する? 黒羽さんと?
もちろんそれを望んでいた。いきなりそうなる展開は考えなかったけど。
彼が好きだった。こんな風にキスして、抱き合って、身体だって欲しい。
でも、それで?
黒羽さんと寝て、オレは何か彼に与えられるものを持っているのか?
「海里。ここでしても、僕はいいよ」
黒羽さんの指が、顔が、唇が、オレを誘う。
「黒羽…さん」
「海里、僕も君が欲しい」
黒羽さんはネクタイを緩め、首から外した。
スルリと絹の冷たい音がする。
黒羽さんだ。オレの身体の下にいるのは、確かに黒羽さんだった。
でも……。
この黒羽さんは、オレが知っている黒羽さんとは違っていた。
どこまでも綺麗で、誠実で。
余計なものをそぎ落として、純化していったような。
透明な水みたいな美貌。
もちろん今の彼が嫌なワケじゃない。
こんな風に誘われて、オレはどうにかなりそうだった。
身体はすっかりその気だし、頭にも血が昇って、まともに思考できない。
今すぐにでも抱きしめて、白い肌に唇をつけて、メチャクチャにしたかった。
でもこれは、取り引きなんだ、と思う。
恐ろしく抗いがたい取り引き。
だけど…。
黒羽さんの手が背中から胸にまわり、そして下に延ばされた。
指で触れられたところから、身体が熱くなる。
「…あっ。く…」
耳元で湿った声が囁く。
「…海里。男が初めてなら、僕が全部するから。だから…」

いきなり海里は獣のように唸った。
絡みついてくる黒羽の腕を外し、無理矢理上半身を起こす。
「だ、……ダメ! ダメだ。ダメ。黒羽さん、ごめん」
「海里?」
畳の上に仰向けになったまま、黒羽さんはポカンとした顔をしていた。
それはそうだろう。
だって、ダメだって言いながら、下半身はしっかり反応してるし、ホント言うと、未練いっぱいで泣きたいくらいだった。
でもダメだ。ダメなんだ。だって…。
「だって…オレ。ごめん、黒羽さん。オレは嘘をついたんだ。情報なんて持ってないんだ」
知らず歯を食いしばる。
バカだオレ。
好きなのに。本当に黒羽さんの事が真剣に好きなのに。
初めて本気になった人なのに。なのに取り引きみたいに冬馬涼一の名前を出して。
自己嫌悪がうず巻く。
ダメだ、こんな取り引き、全然ダメだ。
こんなんで黒羽さんと寝ても、絶対に後悔する。
だいたいオレは、本当に冬馬涼一の情報を持っていない。
「持ってない? でも冬馬涼一の名前は?」
黒羽さんは下になったまま、軽く首を傾げた。
指が伸びて海里の顎の辺りを撫でる。
「……っ」
頬にぞくぞくと快感がはしる。
触れられただけで気持ちいい。白くて長い指。
何度も想像した。その指がオレに触れたら…。
海里は頭を横に振った。
「冬馬涼一の名前なんて、あてずっぼうなんだ」
「それは嘘だ。冬馬の名前は、偶然には出ない」
黒羽さんの透明な水のような瞳が、こちらを見ていた。
その中には、無様なオレが映っている。
もちろんこんなチャンスが滅多にないことは解っていた。
でも……だけど。
ここで手に入れたら、これから先の彼との関係は、全て取り引きだ。
そうなりたいのか?
そりゃあ抱きしめたいさ。抱きしめてキスして、おかしくなりそうだ。
でも、初めて本気で好きになった人と、そういう関係になりたいのか?
取り引きの対象になりたいのか?
「ホントに…知らないんだ。今は」
掠れた苦しい声で、やっと言い足す。
黒羽は軽く瞬くと、メガネを直しながら上半身を起こし、うつむいて座り込む海里のこめかみにキスをした。
「…黒羽…さん?」
「海里、だったらいいよ。情報はいらない。セックスだけしよう」
セックスだけ?
こんなに情けないオレと?
海里は目を瞑って、首を横に振った。
黒羽さんの指は、何かをねだるように身体をまさぐってくる。
一瞬で理性なんて吹き飛びそうな感覚。
けど、でも…。
じっと黙っていると、ふっと黒羽さんの指が離れていった。
やっとオレは、再び彼の顔を見ることが出来た。
黒羽さんの瞳は、まだオレを誘っていた。
薄く目を細めてこちらを見つめる。
あのクールな美貌が、今は妖しいくらいの色気を放っている。
「海里…。今がダメなら、いつでも構わないよ」
黒羽さんはシャツを直し、ネクタイをもう一度首に捲いた。
「ごめん。呼び出しておいて…オレ…」
黒羽さんは何も言わずに、黙ってジャケットをはおった。
帰ってしまう。
もちろんそうだろう。
オレがこのザマじゃ、もうここにいる価値はない。
あまりの情けなさに黒羽さんの方を見ることが出来ない。
しかし靴を履く音がした瞬間、オレは顔をあげてしまった。
「待って」
黒羽さんが振り返る。
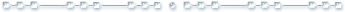
「待ってくれ。た、確かに今のオレは何も知らない。情報も持ってない。それはホントなんだ。でも、映画祭が来たら。来たら、オレ調べるつもりだから。し、翔子が、来るんだ。だから……」
黒羽さんは軽く首を傾げた。
畜生。オレはこれ以上何を喋ろうっていうんだ。
ほんの僅かな時間でも、彼を引き止めておきたいのか?
取り引きは嫌だと思ったくせに、それでも少しでも自分の価値を知らせておきたいのか。
「翔子、とは?」
「た、篁 翔子。ポスターに名前が載ってる。女優だよ。オレは、オレはこんなだけど、でも、篁なんだ」
「ああ……」
黒羽が何かに思いあたったように頷いた。
「篁 翔子は、オレの親戚だ。多分、この映画祭で婚約発表をするはずだ。…冬馬祐二と」
冬馬の言葉に、黒羽は敏感に反応した。
海里を見つめる瞳の光が強くなる。
「本当に?」
「み、未確認情報だけど、でも篁ならするさ。オレは一族の体質をよく知ってるんだ」
あれだけ嫌悪していたくせに、黒羽さんにこんな風に自分を見つめてもらうために、篁の名前を使う。
……オレは卑怯者だ。
海里の声は震えた。
「翔子と連絡が取れるかは、ちょっと解らないんだけど。でも婚約発表なら冬馬の一族が来るだろ? もしかしたら冬馬涼一も出てくるかもしれない。そうしたら…」
海里の言葉はそこで凍り付いた。
いきなり全身に冷水が浴びせられたように、冷たい寒気が身体を走る。
なに?
オレはまた、何か間違えたか?
見上げた黒羽 高の唇には、薄い笑いが貼りついていた。
感情の感じられない、形だけ借りてきたような虚ろな笑い。
やがてゆっくりと、黒羽は人形のような無機質な唇を開いた。
「冬馬涼一は、死んでいるんだ」
「……えっ!?」
オレは馬鹿面を曝していたと思う。ポカンと口を開き、呆然と黒羽さんを見つめる。
黒羽さんは薄く笑ったまま淡々と続けた。
「冬馬涼一は7年前に死んでいる。それでも僕は、彼の今の動きを知りたい。そういうことなんだ、海里さん」
目が驚きに見開かれる。
オレは初めて、自分が本気で何も知らなかったことを知った。
まさか……。
冬馬涼一も、体温の無い男なのか?
オレの表情を見て、黒羽さんは妙に優しく笑った。
バレた、と思う。
自分が実は何も知らないのだという事が、黒羽さんにばれてしまった。
「……海里」
黒羽さんはもう一度近くまで来て、オレにキスをした。
唇を舐めて、軽くついばんでいく。
「海里、いいよ。セックスだけでもいい。いつでも、連絡を待ってる」
唇の感触に、オレは泣きそうになった。
その言葉が言葉通りの意味ではないことをオレは解っていた。
黒羽さんは見做したのだ。
オレが、情報とセックスを交換できる取引相手だと。
再び靴を履く音が聞こえ、ドアが開かれる。
黒羽さんが行く。
行ってしまう。
なのにオレは、見送るために顔を上げることもできなかった。
遠ざかっていく靴音を、オレはうつむいたまま聞いた。

黒羽さんは、もう最初に会った黒羽さんじゃない。
素直じゃないオレに
「あなたは間違っていない」と言い、
「あなたのことは忘れない」と言ってくれた黒羽さんじゃない。
モノクロの中に薄く色が仄めいたような、優しい笑顔。
透明な水みたいな、綺麗な顔。
もちろんオレを誘う黒羽さんも、魅力的だった。
吃驚するほど色っぽくて。
耳元で囁く、掠れた誘惑の声。
あんなに近くに座って、話して、抱きしめて。肌に触れて…
前よりもずっとずっと、オレはあんたに焦がれてる。
でも……。
すうっと、暖かいものが頬を伝い落ちていく。
あんな風な笑顔は、もうオレに向けてくれないのか?
オレは何か間違えたのか?
オレが欲しかったのは取り引きなんかじゃなかったのに。
オレは、まともな恋愛をしてこなかったから…。
オレは…バカだ。
海里は泣いた。
本当に悲しくて泣いた。
涙は、苦かった。

END

|