過去−dark past3−
冬馬涼一。
彼の事を愛していると思っていた。
なのに、僕は彼の事を何も知らなかった。
…いや、彼が知られたくないと思っていたのだ。
だから僕は、彼の望む通り、彼に関して何も見ないようにしていたのだ。
僕は…彼の人形だった。
彼に造られた、彼の玩具。
そんなものに、僕はいつからなってしまったのか。
彼以外の男に抱かれる時、いつも自分は出来るだけ無感覚になるように心がけてきた。
身体だけ。心はどこかに彷徨わせる。
全ての疑問も、自分の気持ちも、心の奥深くに押し込める。
頭の中を真っ白にして、ただ、身体の感覚だけを追っていく。
射精できれば、いいんだから。
そうすれば彼以外の男に抱かれても、快感を得る事ができた。
セックスしている相手を、涼一だと思えばいい。
涼一にしてもらってるって。
だって他の男に抱かれているのは、涼一が望んでいるからだもの。
だから…一緒だ。
涼一の手で、涼一の身体で。
僕を愛してくれるって。
そう…なんだろう? 涼一。
僕はいい子に…。
いい子に…してるから。
だから、おいていかないで。
りょういち…。
「…っ!」
あやうく、彼の名前が口からでる所だった。
あんなに気をつけていたのに、一瞬ぶっ飛んでいたらしい。
今の相手。この男は、思ったよりもセックスが上手かった。
同じセックスをするなら、上手な相手の方がいい。
どうせ身体だけなのだから、他のものは必要ない。
しかし殆どの男は、たいてい黒羽を持て余した。
男とセックスするためのテクニックは、彼からたたき込まれていたから、黒羽が大体の場合はリードをとった。
時には要求されない大胆な事もやる。
無機質な美貌の黒羽がベッドで乱れる姿に、男達は喜んだ。
氷のように冷たそうに見えるのに、一度身体の下で溶け出したら、堪らない熱さになる。
味を覚えたら、忘れられない。
そんな風に噂されているの事を、黒羽自身もなんとなく知っていた。
情報を持ってくる事と、秘密厳守。
これだけが黒羽と寝る為の条件だった。
それさえ守れば、誰とでも寝た。
不思議とその条件は絶対のものとして男達に受け入れられた。
黒羽に関して何かを詮索しようとする人間は、他の男達によって排除された。
まるで薄暗い、秘密のアイドルのように。
誰とでも寝るが、誰のものにもならない。
黒い羽を纏った、セックスの偶像。
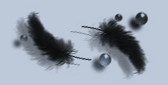
「俺の所に、あんたが降臨してくれるなんて、思わなかったぜ」
男は黒羽の身体に覆い被さっていく。
「降臨?」
黒羽は微かに首を傾げた。
「だってあんた、幻のように噂されてたんだぜ。ホントにいるって、俺は信じていなかったよ」
ああ…と思う。
上には半年以上出てなかった。
冬馬の情報は、一年以上もぷっつりと途切れてしまっている。
彼を追う事をやめるつもりはないが、ほんの少し疲れていた事も確かだった。
それにしても、上に上がってきているというのに、降臨だなんて、まるで何かの冗談のようだ。
「あっ…」
男に身体の奥を刺戟されて、思わず声が出た。
男は夢中になって、黒羽のいい所を攻めたてる。
黒羽は男の身体に脚をからみつけて、一緒に動いた。
「噂、通りだ…いや、ホントに。いいよ、あんた」
「いい…。もっと。もっと奥まで」
男は思いきり腰を突き上げる。
「…っ」
涼一…。
声が、出そうになった。
頭の中が白くなっていく。
彼を憎んでいる。
その筈だった。
なのにこんな時、黒羽が思い浮かべるのは、彼、冬馬涼一だった。
虚無感のようなものが、胸の中にどうしようもなく拡がる。
僕は他の男に抱かれる時、冬馬に抱かれることを考えながら、男達の慰みものになっていた。
『彼』に抱かれているんだと思う。
これは彼のキス。彼の愛撫。彼のペニス。
彼がしたい事を、他の男にやらせているだけだ。
僕には理解できないけれど、それでもこれは、涼一の望みだ。
だから僕は、彼に抱かれている。
いい子にしていれば、愛していると、言ってくれる。
なのに…。
なのに今はどうすればいいんだろう。
セックスの欲望は確かにあるが、他の男に抱かれたいわけじゃない。
そして今は、彼を。
あの男を憎んでいるのに。
しかし…。他にどうしていいか解らなかった。
憎んでいるあの男に抱かれる事を思いながら、黒羽は他の男に抱かれた。
それしかできない。
他の方法を知らない。
鈍い自己嫌悪が自らを包む。
『彼』を追ってどうするつもりなのか、実はよく解っていなかった。
憎んでいると思う。
会ったら、殺してやろう。
そうも思った。
だが同時に、彼に抱かれる事を思うと、どこまでも身体が熱く溶けていく。
悲鳴を上げてベッドの上で乱れる黒羽に、男は興奮し、激しく黒羽の体を責めたてていく。
「もっと…」
もっと、涼一。
「メチャクチャに…」
僕の身体を姦して、あんたのものにしてくれ。
「ああ…ああ…ああぁっ…」
男の手が荒々しく黒羽の勃ちあがったモノを擦りたてる。
黒羽は体を反らし、亢ったものを一気に男の手の中に放った。
――すごく、いいよ、涼一。
このまま…殺して――
真っ白な頭の中で、何もかもが冷たかった、あの男が、チラリと笑ったような気がした。

「行方不明?」
「ああ…」
男は黒羽の身体を撫でながら、ぼそぼそと話を続けた。
「何人か、続けていなくなった。もっともこの辺りは流れてくるヤツも多いし、いなくなった所で酒の話題にもならないんだけど」
「だけど?」
「…気色悪い話なんだ」
「…」
黒羽が黙って男の顔を見つめると、男は重い口を開いた。
「死んだはずのヤツが、帰ってくるって言うんだ」
「ふうん」
黒羽の瞳が、微かに光る。
「いなくなって、死んだんだって。それならそれでいい。何かトラブルに巻きこまれるなんざ、日常茶飯事だ。けど、死んだはずのヤツが歩いてたって、そういうんだ」
「幽霊に、会ったのか?」
「そうだな。死んでいるなら幽霊かもしれない。だが、実体がある。どこか虚ろな目をして、おかしな事を喋る。同じ人間なんだが、どこかが違う」
「冷たい身体をしている?」
黒羽の呟きに、男は頷いた。
「墓場から甦ってくる死体の話を知っているか? 確かに死んだ筈のヤツが、帰ってくるんだ。ただし、半分何かが欠けた姿で」
「見たのか?」
黒羽が問うと、男はぶるっと震えて答えなかった。
「その話…。もしも後で何かまた聞いたら、教えてくれないか」
黒羽は男の耳元で囁きながら、彼の脚の間をまさぐった。
「こんな話が、聞きたいのか?」
「ああ。そういう話が好きなんだ。あんたのここと同じくらい」
男はごくりと喉を鳴らした。
「あまり、話したくないんだが、でも。…あんたに会えるなら、いいか」

しばらく後に、その話をした男も、どこかへと消えた。
彼に会ったという人の話は、まだ聞かない。
だが、冷たい身体で、もしも帰ってくる事があったとしても、それはもう彼じゃないだろう。
二度と彼とセックスが出来ないのかと思うと、ほんの少しだけ惜しい気もした。
END

|