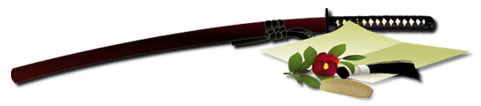妖の刀
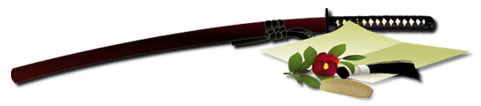
「先生、足元に気をつけてくださいよ」
「わかってる」
薄暗い洞窟のような場所は、入口付近の地面が傾斜している。
奥へ奥へと、ゆるやかに下っているのだ。
「あんまり下へ行かないでください。危険ですから」
「危険?」
「ご存知でしょう。このあたりに出る化け物のこと」
先生と呼ばれた男は凄みのある笑い顔を作った。
だが、薄闇の中にいるのが本人以外には、懐中電灯を持って後ろからついてくる小男ひとりでは、その表情に隠された自嘲を読み取る者もいない。
そのはずだったのだが。
前方でガタンと音がする。
自然現象ではなく、あきらかにそこにいる誰かがたてた音だった。
「誰か、いるのか!」
懐中電灯を持った小男は声を張り上げて誰何したが、語尾が震えている。
「まさか、ジャンク……?」
「それなら、面白いが」
「冗談じゃありませんよ。早く外へ出ましょう」
「逃げたいなら、ひとりで行け」
吐き捨てるようにそう言った男が腰を落として半歩前へ足を出す。
細長い棒のようなものを左手に持ち、右手で棒の端を握った。
とたんに奥から何者かが目の前に飛び出してくる。
それが何かを確認するよりも先に、男の体が反射的に動いた。
後ろにいた小男には何が起きたのかわからなかった。
先生と呼ばれた男が、左手に持っていた日本刀を右手で抜きざまに真横に払ったのだ。
ふたりの前に、ドサッと音を立てて倒れたものがある。
それへ、小男が懐中電灯の灯りを向けた。
「ジャンクじゃない、ただの浮浪者だ」
「なんだ、残念だったな。せっかくのいいチャンスだったのに」
日本刀を鞘に収めた男は出口に向かって歩きだしている。
そのあとを小男が慌てて追いかけた。
二人の姿が消えて数分経ってから、闇の奥からもう一人の男が現れた。
このディープを住まいにしていた浮浪者は一人ではなかったのだ。

「休暇明けの朝一で、桜庭主任に呼び出し受けるなんて、なんの話だろう。
コウ、なにか聞いてる?」
「いや、なにも聞いてない」
「だよね、コウだってオレと一緒に休暇中だったんだもんな」
「香澄、まさか、違うとは思うが……」
真面目な表情の黒羽 高の白い頬が赤くなった。
白鳥香澄にも思いあたることがある。
でも、まさか、あんな場所で二人であんなことをしていたなんて、桜庭主任が知っているわけがない。
警察官としてはあるまじき行為かもしれないが、休暇中の恋人同士にとっては……。
まあ、あんまり、その、堂々と人に話せることじゃないけど、法律に触れてはいないはずだ。
ひょっとして、わいせつ物陳列罪とかに問われたら、言い訳はできないけれど。
この二人が休暇中にいったいどこで何をしたのかは関係なかった。
(気になるけど)
「コウ、ちょっと……」
「ん?」
署内の廊下を黒羽と並んで歩いていた香澄が足を止める。
香澄の手が黒羽の首筋に伸ばされて、指先が襟元近くの肌に触れた。
まさか、こんなところでキスしようとしているのか?
それならそれで応じようと黒羽は背をかがめた。
黒羽は気にしていないが、香澄は自分のほうが背が低いことをすごく気にしているのだ。
「ここ、赤いの消えなかったな」
香澄が触れた場所には、誰がどう見てもあきらかなキスマークがくっきりとついていた。
「あ……」
なにを思い出したのか、黒羽の白い肌が赤く染まる。
アンダー育ちの黒羽は、本物の太陽光線に殆どあたったことがない。
その真っ白な肌が、羞恥に赤く染まっていた。
正義の味方「レフトハンドショットガン」黒羽 高は、警察のあらゆるポスターのモデルになっている。
人並みはずれた容姿と美貌だけでなく、銃の腕前、地道な捜査、正確で素早い判断力、なにをとっても黒羽 高の右に出る者はいない。
だが、黒羽には人には言えない過去があった。
過去というには生々しすぎる記憶。
まだ本当には解決していない自身の問題を抱えている。
それを受け止めてくれるのは香澄だけだ。
砂城の警察に外からやってきた香澄は、黒羽の仕事上のパートナーになっただけではなかった。
香澄は子供の頃から憧れていた黒羽 高のすべてを受け止める覚悟でいる。
それは、桜庭主任に頼まれたからというだけではない。
黒羽の意外に脆い一面を知ったからかもしれなかった。

「君たちにお客様よ」
桜庭主任の近くの椅子に背中を向けて座っている人物が振り向いた。
「お久しぶりです」
「どちらさまですか?」
黒羽と香澄が同時に声を発する。
香澄が知らない人物は、黒羽の剣道の師だった。
「全然顔を見せんから忘れてしまったぞ、と言いたいところだが、おまえさんの顔は忘れたくても忘れらないないな。街中のどこにいてもポスターが貼ってある」
小柄な老人だが、鍛えられた肉体を持っていることは、その若者のように身軽な動作でわかる。
飄々とした人物だ。
「新しいパートナーは、ずいぶん若いようだなあ」
香澄の顔と黒羽の首筋を交互に見る老人の顔に好色そうな笑みが浮かんだ。
白鳥香澄は二十歳、黒羽高は二十七歳。
しかも、香澄は典型的な童顔だ。
若く見られるのには慣れていたが、黒羽を見る老人の好色そうな笑みに香澄はムッとした。
「おまえさんたちに、頼みたいことがあるんだが……」
人にものを頼むときの態度ってもんを知らないのか、このジジイ。
と、香澄が心の中でつぶやいたことを誰も知らなかったのは幸いだった。

「香澄、足元に気をつけて」
「わかってる」
香澄がディープに入るのは初めてではなかったが、いつも緊張する。
それは香澄が臆病だからというわけではない。
ディープにいるときに気を抜いていたら、それこそ危険だから緊張している必要があるのだ。
ここは浮浪者が切り殺された事件現場だった。
「思ったより狭いなあ、こんな場所で日本刀を振り回すことなんかできないんじゃないの?」
「うん、だけど、振り回さなければ……」
黒羽がなにかを考えている。
懐中電灯の淡い光に照らされた横顔が美しい。
香澄はよからぬことを妄想してしまった。
黒羽が地面の少し低いところに立っているので、身長が同じくらいになったみたいに感じる。
今なら、背伸びしなくてもキスできる。
そう思ったら、止められなかった。
「コウ」
呼ばれて振り向いた黒羽を抱き寄せて唇を重ねる。
細身だがしっかり筋肉がついた男の身体に欲情する自分が不思議だったが、それは相手が黒羽 高だからだ。
「んっ……ふ……」
舌を絡めとられた黒羽が甘い息を鼻から漏らす。
これ以上キスしてたらマズイことになりそうだ。
香澄は慌てて黒羽から身体を離した。
警察独身寮の大浴場の湯船に二人でつかっていた。
ここの熱い湯に、香澄もだいぶ慣れてきている。
「その浮浪者を切った刃物って、本当に日本刀だったのかなあ」
「目撃者の話と検死結果からみれば、そういうことになる」
「コウは、あの狭い地下でそんなことができると思う?」
黒羽はしばらく考えてから答えた。
「できる、と思う」
黒羽の白くて滑らかな肌が熱い湯でピンクに染まって色っぽいことこの上なかったが、周りには数人の同僚たちがいるので香澄は指を咥えて見ているしかなかった。
「使われたのは、あのおじいさんが盗まれたっていう日本刀なのかな?」
「確信はないけど、たぶん」
黒羽がこんなふうに言うのは珍しかった。
根拠のないことを信じるなんて、香澄が知っている黒羽の言う言葉とは思えない。
それだけ、あの老人を信用しているということなのだろう。
事件現場は西署の管轄区域内ではない。
本来なら黒羽と香澄が担当することはないはずだ。
それを、強引にそうさせてしまえるなんて、あの老人ただ者じゃないな。
それにしても、コウと一緒に大浴場に入るのは危険な行為だ。
身体の一部が反応してしまっていることを誰かに見られたら困る。
それよりもっと困るのは、誰もいない大浴場に二人きりになったときだ。
コウはためらわずに仕掛けてくるけど、こんな場所で落ち着いてできるわけなんかない。
けど、しちゃうんだよな。オレってば、若いし。
そんなことを考えている香澄の目の前で、黒羽が湯船から立ち上がった。
目の前にコウのアレが……。
香澄は頭がグルグルしてきた。
熱い湯に長くつかりすぎたせいだった。

「わざわざ来てもらって、すまないのう」
「ご無沙汰してしまって、申し訳ありません」
「いいんじゃよ、ワシは引退したんだ。道場は息子がやっておる」
引退したと言いながら、顔じゅうに皺を寄せて笑っている老人の、目だけは鋭く光っていた。
「これを見てもらいたい」
老人の目の前に置かれているのは大小二本の刀だ。
盗まれたんじゃなかったのか?
と、一瞬、香澄は思ったがすぐに盗まれた日本刀とは別物だとわかった。
それよりも、さっきからずっと畳に正座しているので足がしびれてきた。
隣りを見ると黒羽は、平気な顔をして正座している。
「足をくずして、かまわないぞ」
この老人の言い方はいちいち香澄の感に触ったが、足のほうはすでに限界を超えて感覚がなくなりつつあったので、素直にあぐらをかいた。
「ワシの家から盗み出されたのは、村正だったんじゃよ」
「では、これは……」
「知人に頼み込んで借り受けてきた刀だ」
「拝見します」
黒羽が鞘から刀身を抜く。
しばらく黙って眺めてから元に納めて、次に小刀も同じように見た。
「名のある刀なんですね」
「わかるか」
「銘までは、わかりません」
「うむ……」
老人が刀の説明を始める。
「大刀の名は小篠(をざさ)、小刀の名は落葉(おちば)、妖刀と言われている刀のひとつじゃ」
黒羽と香澄は、同時に首をひねった。
「両刀で、雪篠(ゆきざさ)と呼ばれておる」
背筋を伸ばして正座した黒羽が正面から老人の顔をみつめて言う。
「今回の事件に使われた村正も妖刀と呼ばれていますね。そのことが関係してるということでしょうか」
黒羽にみつめられた老人は、なぜか皺だらけの顔を赤らめた。
「実はな、ワシのほかにも村正を盗まれたと言っている者がいるんじゃが、どうも、そいつの所有していた村正は贋物だったらしいんじゃ」
黒羽に正対して座っている老人が、ふたりのあいだに置かれていた刀を脇へどけると、膝が触れ合わんばかりに近寄ってきた。
「犯人は、何らかの理由で妖刀を狙っている。それは間違いないんじゃ」
今や、ふたりの膝頭はぴったりとくっついて、老人の手が黒羽の太腿に伸ばされようとしていた。
老人のセクハラである。
恋人の危機に、ちっとも気づかずに考え込んでいた香澄がいきなり大声をあげた。
「ああーっ! 思い出したぁ!」
あと、ほんの少しで黒羽の太腿に触れそうになっていた老人が残念そうに手を引っ込める。
「なんじゃ、いきなり大きな声を出しおって」
「香澄、なにを思い出したんですか?」
香澄は二本の刀を指差して言った。
「これこれ、この刀って、里見八犬伝に出てくる日本刀ですよね」
老人の眼がキラリと光る。
「若いのに、よく知っていたな」
「意外ですね。香澄が南総里見八犬伝を読んでいたなんて」
「読んでないよ、子供の頃テレビで観たんだ。人形劇の里見八犬伝、面白かったなあ」
老人は、そんなことだろうと思ったと言いたそうに不快な表情を浮かべた。
黒羽には、香澄の言っていることがわからないようだった。
「テレビで放送してたじゃん、オレが観たのはもちろん再放送だけどさ」
黒羽は相変わらず首をひねっているし、老人は呆れ顔で自分を見ていることに気づいて香澄は取り繕うように話し続けた。
「その刀って、犬川荘助の刀だよね。刀を取り合って犬士同士で闘ったり、いろいろあったけど最後には荘助が所有することになるんだよ」
いきおいよくしゃべり続けていた香澄がふいに黙って、腕を組んでウンウンうなりながら考え込んでいる。
老人と黒羽は、香澄の様子につい見入ってしまっていた。
「あれ? おかしいなあ」
「何が、おかしいんですか、香澄?」
おかしいのは、お前の挙動だ。と、老人が心の中でツッコミを入れた。
「里見八犬伝って、架空の話だよね。その刀がなんで本当にあるのかなあ?」
「それは……」
老人が真顔に戻って説明を始める。
「あの話は、歴史の虚実を取り混ぜて書かれておる。どれが本当のことで、どれが作り事なのか、正確なところは誰にもわからんじゃろう。だから、この刀が実在していてもおかしくはない」
「それは、その刀が本物じゃないってことですか?」
「そうは言っておらん」
黒羽は、香澄の鋭い洞察力に感心させられた。
香澄はときどき鋭い。
仕事のときだけじゃなくプライベートでもそうだ。
黒羽がどんなことを望んでいるのかを、本人よりも香澄のほうがよく知っている。
こんなときなのに、黒羽は休暇中のことを思い出して身体を火照らせてしまった。
(休暇中に二人が何をしたのかは、関係ないので割愛します)
黒羽の心が別の場所に行っていることにも気づかずに、老人と香澄は八犬士の武勇伝で盛り上がっていた。意外と気が合っているようだ。

next

|