第三章 「撮影開始−海里の告白」
さっさと撮って、とっとと帰らせる。
そんなつもりの白鳥と黒羽だったが、もちろん実際はそうはいかなかった。
撮影のベストポイントを捜すために、ホテルの敷地中を歩き回る羽目になる。
「オレは一応プロだからな。その辺のシロート写真を撮ってたまるか」
こだわる海里に引きずり回され、やっとポイントが決まったと思ったら、海里が今度はメイクをすると言い出した。
「はあ? メイク? コウは男だぞ」
「するんだよ、バカ。テレビに出ている人とかは男だってメイクしてんだ。でないと綺麗に映らないだろ?」
「そ、そうなのか?」
「いくらスナップ写真風だって言ったって、一応雑誌に載るもんなんだ。おまえだって黒羽さんが綺麗に映った方がいいだろ?
それに肌、あんまりよくないっておまえも言ってたじゃないか。メイクはする。解ったな」
「う…うん」
白鳥は海里のペースにすっかり巻き込まれていた。
なにせ自分の全然知らない世界だ。相手が言っている事の何が本当に必要で、何がそうでないのか区別が付かない。
ただ頷くしかなかった。
しかしさすがに海里が黒羽一人を連れてどこかへ行こうとした時には、抗議の声をあげた。
「おいっ、どこ行くんだよ」
「メイクしに行くの。向こうの影に洗面所がある」
「ここでやりゃいいじゃん」
「うっせえなあ。洗面所には鏡があるだろうが」
唇をとがらす白鳥に向かって、海里は持参した紙袋の中から何かをポイポイと投げてよこした。
「うわっ。なんだ、てめえ」
台所で使う様なアルミホイルのロール。白いガムテープ。厚紙何枚か。
「???」
首を捻る白鳥に、海里は離れた所から指を突きつけて命令した。
「メイクしてる間、おまえはそれでレフ板作っとけ」
「…レフ?」
首を捻る白鳥に、松本がニコニコ笑いながら説明した。
「これで太陽の光を反射させて、顔を明るく映すんですよ。写真のテクニック」
「太陽って、こんなにきっぱり出てるじゃん。このまま写す訳じゃないの?」
「きっぱり出てるから、逆に顔に影が出来るでしょ?」
「フラッシュは?」
「ううーん。説明難しいんだけど。フラッシュだとやっぱり陰影がキツく出ちゃうんだよねえ」
「はあ…」
ぼけっと説明を受けている白鳥を横目で眺めながら、海里は人気のない洗面所の中に黒羽を連れて入っていった。
「いいね、一流ホテルの洗面所って。広くて綺麗で明るい。黒羽さん、ここ座って」
なんだか知らないが、トイレのくせに座るための椅子までついている。
黒羽は言われるままそこに腰掛けた。
「うん…」
海里は紙袋の中からメイク道具らしきものを取り出すと、にっこり笑って黒羽の顔を見下ろした。
「海里?」
「黒羽さん、やっと二人きりになれたな」
|
「香澄ちゃん制作。簡単レフ板の作り方」
1:台所のアルミホイルを優しく丸める。
2:ていねいに広げる。
3:白い厚紙を広げ、両面テープを均一に貼る。
4:その上に、押しつけるようにしてアルミホイルを貼る。
5:まわりを白いガムテープでかがってできあがり。
撮影とかで板のようなものを上に掲げている人がいますが
それがレフ板です。
|

「ずっとそっぽ向いてんだもんな。あのチビもひっついてるし。やっと二人っきりだ」
海里から笑いかけられると、ドキリとした。
自分はこんな風に笑う男に弱い。
慌てて立ちあがろうとしたが、海里に上から押さえつけられた。
「写真撮らせてくれるんだろ?」
言いながら黒羽の髪をピンで留めはじめる。
「メイクの専門家じゃないから、適当だぜ。オレはホントはスタジオ写真家じゃないんだ。まあ頼まれれば何でもやるけど」
コットンに含ませたローションで顔全体を拭く。
「黒羽さん、目を閉じて。よく拭かないとメイクのノリ悪いから」
言われるままに目を閉じると、コットンの感覚だけが顔を滑っていった。
こんな事をしたのは初めてだが、悪い感じじゃない。
人に触れられる事は気持ちいい…。
海里の指が頬に、顎に、瞼に触る。柔らかくマッサージするように動く。
黒羽はその感覚を楽しんだ。
だが次の瞬間、何か柔らかく暖かいものが唇に押し当てられた。
「ん…」
それは黒羽の中に押し入り、口の中を探る。
「ん…あ…」
「黒羽さん…」
海里は黒羽の上に覆い被さるようにして、更に深く唇を合わせてきた。
「ひどいよ黒羽さん。逃げるなんてさ。あんたにあのチビがいる事は知ってる。だけどオレだって本気なんだ」
「あ…海里」
「さっきだって見せつけてたんだろ? 恋人だって、わざわざ言って。ひでえや」
海里のキスから逃れる事が出来なかった。
痺れるような感覚が身体の中に走る。
「あんたがあいつとキスしてセックスしてる。そう考えたらオレ…。なんかもう頭の中がどうにかなっちゃいそうだよ」
海里の手が黒羽のズボンに伸びてきた。
「あっ…」
いちばん敏感な部分に触れてくる。
「あいつもこうする? こんな風に?」
ボタンが外され、手が中にすべり込む。
「かい…り」
「知ってる。あんたとあいつが恋人同士だって事は。だけど、オレもあんたが欲しいんだ」
逃げる事は、今度はできそうになかった。
「ビックリした。黒羽さん、あんたがいるんだもん」
海里の手は身体をまさぐり続ける。
「行先はオレと同じだって知ってたけど、でも会えるなんて思ってなかった。なんか感動しちゃったよ。すげえ偶然。
オレ運命とか信じないほうなんだけど、ちょっと信じたくなってきた」
「あっ…。かい、り…。ん…。」
拒絶できない黒羽に勇気づけられたように、海里はだんだん大胆に振る舞いはじめた。
キスを続けながら、ズボンの中の手は黒羽のモノを握って軽く扱く。
黒羽の息が甘く乱れた。
「やだな、オレ…。こんな事したの初めてだ。だけど興奮しちゃうな。あんたのここに触れるなんて」
「海里…。お願いだ。やめ…。僕の話を…」
「逃げられた時、仕方ないと思った。当分会えないかもって。だけど…ここで会えた。逃がしたくない」
これは裏切りだ。
身体だけならともかく、心が揺れている。
いや、恋人は香澄だと思う。
香澄以外に考えられない。
彼の隣が今の僕の場所だし、そのうち家を買って彼と住むんだ。
約束をした。
遠い約束で僕にはまだよく解らないのだけど。
でもどこまでも暖かく柔らかい、せつない未来の夢だった。
なのに、身体は裏切っていた。
海里のしている行為に体が熱くなる。
熱を帯びて興奮する。
純粋なセックスの欲望がせりあがって疼いた。
香澄と、最近してなかったな、と思う。
旅行に行く前は、長期の不在に備えてたまっていた仕事を片づけたり、整理をしたりで何日も何日も、えらく忙しかった。
ホテルに着いたその日は夜で、疲れてそのまま寝てしまった。
そして昨日は香澄とバスルームでほんの少しふざけたきりだ。
セックスとは、しばらくご無沙汰だった。
海里の指と男の匂いが欲望を刺激する。
けっして欲求不満だった訳ではないが、この状況が余計そうさせるのだろう。
男が欲しい。それだけなら良かった。
(いや、香澄はきっとそれも許さないだろうが)
単純な欲望なら、それ程怖くない。
自分は男で、男の欲望は、時に心と切り離されて存在する。
そして更にゲイだから、同性に欲情して体が反応する。
香澄と会う前、冬馬に捨てられてからも、体が求めれば男と寝た。
目的があった事もあるが、どれも体だけの関係だ。
そして自分の中で、身体はあまり大切なものではなかった。
傷を付けても平気だし、欲しいと言われれば、あまり躊躇することなく与える。
肉体を誰かに差し出す事は、自分の中では比較的簡単な事なのだ。
香澄と関係を持ってからも、その認識は変わらなかった。
誰かと寝る事は大したことではない。
あっさりと越えられるハードルだった。
香澄とだって、出会ってそれ程たたないうちに寝た。
彼が積極的だったなら、もっと早くそうしていただろう。
あの頃は香澄とセックスする事も、他の知らない誰かとする事も一緒だった。
その時海里と知り合っていたなら、何のためらいもなく彼に抱かれていただろう。
だが今は事情が違う。
僕が他の誰かと関係を持ったりしたら、香澄はきっと怒るだろう。
それとも身体だけの関係だったら、納得してくれるだろうか?
香澄ではないので、よく解らなかった。
ただ香澄は自分が軽視しているこの身体を大切に思ってくれている。
僕自身よりもずっと、遙かに身体それ自体にも、価値を見いだしているようだった。
しかし自分は、香澄に想われている事は充分解っていながら、それでも恋人以外の誰かとセックスする事に、あまり禁忌を感じなかった。
冬馬といた頃は、ずっとそうしてきたから。
香澄と過ごした日々で、あれは間違いだったのだと解っても、最初のセックスで覚えた事は、そう簡単には消えなかった。
頭と関係なく身体が反応する。
求められればあっさり体を許してしまう自分が、ふとした弾みに頭をもたげる。
今も、すぐにでも海里に許してしまいそうだった。
海里の愛撫に素直に身体を預けたくなる。
男が初めてにしては、彼の指は巧みだった。
ひとりでに声が唇から漏れる。
それに喜ぶように、海里の指はさらに黒羽自身に絡んだ。
   
「黒羽さん、黒羽さん…」
海里は夢中になって黒羽の唇を舌で探り、手で黒羽のモノを愛撫する。
「海里…ダメだ、服を、汚す…。香澄に」
「ダメなのはそれだけ? だったらオレ、あのチビにバレてもいい。ここで黒羽さんを手に入れたい」
黒羽の手が、ゆっくりと海里の身体に伸びた。
…好きになったのは冬馬と香澄だけだった。
身体の関係があった男はたくさんいたが、心で想ったのは2人だけだった。
冬馬とはもう終わり、今は香澄だけ。
好きなのは、香澄だけ。
真剣な顔で自分を見上げて『黒羽さんとセックスしたい』と言った香澄。
あの時は解らなかったが、今なら少しは解る。
香澄が欲しかったのは身体だけではなかった。
そして自分も本当は心の中では、そんな風に求められる事を強烈に望んでいたのだ。
香澄と何度も抱き合って、初めて自分がこれほどまでに飢えている事に気がついた。
幾度も彼に満たされながら、まだ足りないと思い続ける。
そして、海里も香澄と同じ目をしていた。
身体も心も欲しい。
黒羽を愛したい。心と体で。
それはえらく魅力的な誘いだった。
セックスで愛を感じる事。
自分の中の欠けている部分を相手の身体で埋める事。
ずっと怖かったくせに、それでも自分はそんなものにひどく飢えていた。
ずっと前から、そしてこれから先も。多分…。
まずい。
どんなに魅力的だろうと、それでも彼の気持ちを受け取る訳にはいかない。
黒羽の手は海里の身体を滑り、海里の中心に触れる。
「あっ…。黒羽さん」
海里は驚いたように一瞬身体を引きかけたが、その感触に体を震わせた。
だが黒羽の手は硬く勃ちあがったそれを愛撫しかけて、それからあっさりと離れた。
そして肩を掴むと、海里の体を押し返す。
「黒羽さん?」
いきなりの動きに海里は不意をつかれ、簡単に体を離した。
黒羽は黙って首を振る。
「黒羽…さん…」
黒羽の体はまだ欲望に疼いていた。
海里の勃ちあがったものに視線を走らせると、どうしようもなく欲しくなる。
体だけ欲しいというなら、いますぐに抱かれても構わない気分になっていた。
でも…。
「黒羽さん、やっぱイヤなのか? オレじゃダメか? 全然?」
海里が悲しそうな瞳で黒羽を見下ろした。
腕を伸ばしてくる。
「海里、そうじゃない、そうじゃないけど…」
「寝たいかって聞いたのは黒羽さんじゃないか」
手は再び黒羽の顔を捉える。
「海里、だけど…」
「いいよ、解っているんだ。あんたにはあいつがいる。でもオレ、それでもいいんだ」
手は顔から体に伸び、黒羽を抱きしめようと動いた。
「なあ、それでもいい。オレ二番目でもいいよ。なんとも思われてないのよりマシだ。先がどうなるかなんて解らないけど、今オレを完全に拒否しないでくれ」
「海里、海里…痛い。あっ…」
彼の指が背中を這い、爪が傷めた肌に擦れて引っ掛かる。
「海里、お願いだ…」
黒羽が痛みに顔をしかめ、微かな悲鳴を上げると、海里はハッとしたように体から手を引いた。
「…ご、ごめん。背中痛かったんだよな。ごめん、オレ…」
海里はしょんぼりと下を向く。
皮肉っぽい笑いも、からかうような態度も無くなっていた。
黒羽の前では、いつも自信家の様に振るまい、押しの強い海里。
その彼がいま、自分の感情をもてあまし、途方にくれていた。
二番目でもいいなんて、そんなはず本当はなかった。
思わず口走ってしまったのだろう。
海里が弱さをさらけ出した事に、胸がちくりと痛む。
「海里、僕は君が好きだ」
うつむいていた海里の目が見開いた。
黒羽は、一つ息をつく。
そう、本当の事だ。嘘はつきたくない。
好きになったのはこれで3人。
冬馬と、香澄と、それから…海里。
「だけど応えられない。君の気持ちも解ってて、応えられない事も解っているのに、そのうえ君に甘えるなんて事は出来ない」
彼の真剣な想いに何一つ返せるものがないのに、彼からは快楽と心が欲しいだなんて。
そんな都合のいい、そんな卑怯な真似はできない。
「黒羽さん、あんたやっぱり綺麗だね」
しばらく黙って、やっと海里が口を開いた。
『オレじゃダメか?』そう聞いた時の、少し打ちのめされたような感じは無くなっていた。
うっすら笑いながら、黒羽の顔を見る。
「かまわないじゃないか。オレが二番目でいいって言ってんだから。
チビには黙ってるし、オレは解ってて言ってんだから、真面目に応えなくたっていい。あんたは自分に都合のいいとこだけ取って、オレをあしらう事だって出来るじゃないか」
海里は肩をすくめて首を振る。瞳の中に強い光が戻っていた。
「最初に会った時、なんて綺麗な兄ちゃんだろうって思った。綺麗な男は他にも知らない訳じゃないけど、でも誰もあんたほど印象的じゃない。
ビックリして見蕩れて。そんで、次に会った時は、オレ…」
にっこり笑って見上げる。
「もう好きになってた…」
眩しいくらいの、綺麗な笑顔。
「理屈じゃない。理屈じゃないよ。あんたがこんな風に好きだって気付くのに時間がかかったけど。でも、解って良かった。
オレ、本気であんたに惚れてるんだ。信じられないけど、そうなんだ」
「海里、僕は…」
海里は手を振る。
「そんな顔すんな、黒羽さん。困らせてごめんな。解ったから。
オレ、少なくともあんたに拒否されてる訳じゃない。それだけがすごく怖かった。あんた、逃げるし、食事の時はオレを無視するし」
「…すまない」
「いいのか? 謝ったりして。そんな事すると、オレつけ込むぞ」
「海里」
「オレ、あんたに惚れてるんだから。好きになる事は止められねえよ。あんたが応えてくれなくたっていい。
気にするな。オレの方が勝手に好きなんだから。それに、さっきあんたもオレの事好きだって言ってくれた」
海里はほんの少し下品に笑った。
「だから、今はそれでいいよ。それにもしかしたら状況が変わる可能性だってあるもんな。さっきだってもう少しでなだれ込めそうだったし…。
いや、真剣に考えるなって」
海里がニヤリと笑う。やっといつもの彼だった。
「でもさ、なんならその…。途中までやっちゃったし、黒羽さんの分だけでも、一発抜いてやってもいいぜ。服を汚さないように、口でしようか?」
黒羽は顔を真っ赤にして立ちあがった。

「海里の奴、ちょっと遅いんじゃねえの?」
白鳥はやっと出来上がった簡易レフ板を満足げに眺めながら言った。
「そーお? メイクって時間かかるよ」
白鳥はじろりと松本の顔を睨む。
どーも、一癖も二癖もありそうなおっちゃんだ。
しかも基本的には海里の味方だ。
このおっちゃんがニュートラルな位置にいると勝手に思うのは危険だろう。
「わー、刑事の目だね、それって♪ いいなあ、そうやって常に人を疑って過ごしているのね。ハードボイルドっぽくて格好いい♪」
「あのな…」
何かガクッとする。
どこまで本気だよ。それに今の目は、犯人を追うって言うより、間男を見つける亭主の目…って、言っててオレの方が情けない。
「とにかく遅い! オレ見てくるから」
言い捨てて走った。
やっぱり絶対遅いって。
海里の野郎、もしもコウに手なんか出してやがったら、ただじゃおかねえ。
それにコウだって変だった。
食堂でのあの態度といい。
キョーレツ嬉しかったとはいえ『恋人』だなんてわざわざ言ってみたり。
そりゃまあ、恋人ったって個人の事情ってもんがある。
仲良く円満に過ごすためには、ちょっと位なら色々誤魔化されてやるさ。
嫉妬深くてうるさい男ってのは、何かオレらしくないし。
だけどもちろん我慢できない事だってある。
「コウ、まだなのか?」
オレはまるで不意打ちでもかけるように、いきなりがばっとトイレの中を覗き込んでやった。
だが中には、ボーッと突っ立っている海里が一人いるだけだった。
「ああ? どうした?」
海里が横目でちらりと見る。
「…あり? コウは?」
なんだか拍子抜けだ。
オレの頭の中には、メイクされてるコウか、そうでなけりゃ海里の野郎に押し倒されてるコウか、そのどちらかしか存在しなかったのに。
「黒羽さん? トイレ」
「は?」
「さっき食べた朝食がちょっと悪かったらしいぞ。腹痛いって」
「はあ…」
「…そうだな。じゃ、オレもついでに入っとくか」
言うなり海里は一番近くのドアを開け、バタンと中に閉じこもってしまった。
「………」
いきなりオレってば、一人トイレの中で取り残される格好になってしまった。
個室に入るって事は、小便じゃないんだよな…。
そんな間抜けな事を思いながら。
「あ、香澄…ごめん」
何やらぼけっとトイレからでてきたコウが、オレの顔を見て少しだけ顔を赤くする。
「ええーっと。いや、便所長いなあって思ってさあー」
オレってば特大のボケを口に出す。
バカか?
マジに腹をこわして籠もっていたんなら、個室から出てきた所で恋人と顔を合わせたら、ちょっと気まずいに決まってるだろ?
まあその、コウは女の子じゃないから、それ程気にする必要はないと思うけど。
コウは背中を向けて手を洗っている。
鏡には半分くらいしか顔が映らなくて、表情は解らなかった。

ううむ。だけどそういうシチュエーションって、オレ達が男同士だからありえたって事だよな。
いくら恋人だって、女性用トイレにいきなり押し掛ける度胸はオレにはない。
そんな事したら、一発殴られて、振られてお終いだ。
殴る代わりにコウは振り向くと、オレの顔を見て微かに笑った。
なんとなくオレはドキリとする。
「あ、あ…メイクこれからか? 腹の調子悪いんなら、オレもう少し向こうで待ってるから」
妙にしどろもどろになりながら行きかけたオレの手を掴んで、コウが軽く首を振った。
「いや、待っててくれ。遅くなったのは僕のせいだから」
「う…うん」
「おう、じゃ早くしようぜ」
水を流す音がして、手前の個室から海里が顔を出す。
「ちゃんと手洗えよ」
こいつの顔を見ると、つい癖で突っかかるような言い方しちゃうんだよな、なんて思う。
だが海里は妙にサッパリしたような面をして、オレの挑発には乗らなかった。
「ああ、黒羽さん日焼けひどいからな。ちょっと念入りにやろうぜ」
コウが座ってメイクをしている間、オレは隣で立ってずっと見ているはめになった。
海里の手は思ったより器用に、コウの顔の上を動いていく。
綺麗な顔が、手を入れる事によって更に引き立つ事を、オレは初めて知った。
メイクしている間中、コウはオレの手を掴んだまま離さなかった。
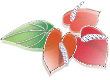
撮影はさっさと終わった。
海里は本当に一枚しか取らなかった。
もっともその一枚をベストショットにするために、シャッターを切るまでの時間が少々長かったが。
「おまえじゃダメだ、おっちゃん交代」
海里が首を振り、オレはレフ板係を即座にクビになる。
「太陽の光をねえ、こう対角線上に受けると…」
松本が何か言いながらコウの顔に光を当てる。
「いや、オレは別にカメラマンになる気はないから」
講釈をいいかげんに聞き流し、オレはコウに視線を移した。
さっきからオレは、ひたすらコウの姿に見とれていたのだ。
蒼い空に、白いホテル。
南国の花咲き乱れる庭の、鮮やかな花の色と緑の影。
その風景に収まるコウは、上から下まで真っ白な服で、なんていうのか、その…。
笑われるから誰にも言うつもりはないが(特に海里には絶対言わねえ)まるで、なんだか天使のように見えた。
鮮やかな色彩の中、そこだけ白く、背景からふわりと抜け出るように存在するコウ。
その雰囲気は、ちょっとだけ人間離れしていた。
黒い髪、黒い瞳。長い睫毛。
神様がさぞ注意して配置したんだろうな、と思う綺麗な白い顔。
なんでこんな人がいるんだろう、とオレは改めて思った。
もう何度も思った事だけど、こんなに綺麗な人が、オレの隣にいるなんて、やっぱり奇跡みたいだった。

「そんじゃなー、また砂城でな黒羽さん」
きっちり黒羽にだけ挨拶をして、海里が手を振る。
「雑誌出たら送りますから」
「あと何日かはこっちにいるんだ。街で会えたらいいな」
「遊んでる訳にはいかないよ。今からが本番の取材なんだから」
「今日から安ホテルかー。朝食もっとたくさん食っとけば良かった」
「あんたねえ、ホントに元いいとこの坊っちゃんなの?」
憎まれ口を叩き合いながら、2人はバスに乗り込んでいった。
バスを見送る黒羽と白鳥の姿が、だんだん小さくなり視界から消える。
海里はそれでもちょっと名残惜しそうに後ろを見ていたが、一つ息をついて視線を前に戻した。
「海里、あんた上手くいった訳?」
「なんの話だよ、おっちゃん」
「何のって、そりゃー、アレだよ、アレ。あの超美形とあれだけ長い間トイレに籠もってて何も無かったなんて言わせないからね」
「へっへっへ…」
「やな笑いだねー。一応協力してやってたのに」
「あっ、そうなんだ。サンキュー」
「感動薄いなあ…。せっかくボクがあんたの為に、黒羽くんあきらめたのに」
「おっちゃん最初からあの人に印象悪いよ」
「解ってるようー、それくらい。だからボクの事はどうでもいいんだよ。あんたの事を聞きたいんだって」
「…いいとこまで行った」
「えっ!? マジマジ? どこまで行ったって?」
「そんな事おっちゃんに言えるかよ」
「協力したのにケチだなあ」
海里はじっと松本の顔を眺めた。
「何? 何だい、気持ち悪い」
「…なあ、おっちゃん、ホモってどんな感じ?」
「ど、どんな感じもこんな感じも…。いきなり何? どういう事?」
「いや、別に。ちょっと聞いてみただけ。たださ、あの人相手なら、もうホモでもいいかって思ってさ」
「きゃー、吹っ切った訳?」
海里はじろりと睨みつけた。
「おっちゃん、オレの前でオカマ言葉はやめろって何度も言ってるだろ?」
「今ホモでもいいかって言ったくせに」
「それとこれとは別。黒羽さんはゲイだけど、オカマ言葉は使わねえぞ」
「…そんなの個人の自由でしょうに」
呟く松本を無視して、海里は鋭く目を細めた。
「あの人が男で、オレも男なんだから、もう仕方ないじゃねえか。解ってたんだよ、ずっと。身体も欲しいって。でもさ、やっぱり色々あるじゃねえか。男が男を、そんな風に好きってのはさ」
「ボクなんて最初からそうだけどねぇ〜」
「でもいいや。オレ決めたわ。男でもホモでもいい。でないと惚れた相手に何も出来ねえ。そんな情けない事、このオレが出来るかよ」
「格好いいー。海里くん。そういうとこ好きだよ」
「おっちゃんじゃねえよ、黒羽さんに好かれたいの」
海里はげんなりしたように首を振った。
そうさ、好きなんだ。
オレ、好きなんだから。
初めてなんだ。こんな風に、どうしようもなく人を好きになるのは。
あのチビがいつも堂々としてやがるから、ずっとちょっと羨ましかった。
オレは長い間、自分の好きな事とかやりたい事とかを押さえ込んで生きてきた。
『家』が許してくれなかった。
その家を捨て、大学を中退して自分のやりたいことをやろうって思ってからも、なかなかその感覚は抜けてくれなかった。
もちろん世間は自分の思い通りになる訳ではない。
駄目な事の方が多いし、邪魔だっていっぱい入る。
だから、だからこそせめて、自分の気持ちには素直でいようと思ってる。
もういいじゃん。
オレホモだっていい。
マジで好きなんだから。
枠の中が嫌いなくせに、ホモが嫌いだって枠を自分で作ってるから、いつまでたってもあのチビに勝てないんだ。
だってあいつ、白鳥香澄。黒羽さんと寝てやがるんだろう?
ただでさえ分が悪いのに、これ以上引いてたまるかよ。
あの人だって、オレの事を嫌いな訳じゃないんだ。
といってもあの2人、基本的には悔しい事に相思相愛だから、道は険しそうだけどな。
ああ、めちゃめちゃ抱きてえ。
道端で触ったあの人の肌。
今日味わった唇の柔らかさ。
ぞくぞくする。
キスして、抱いて、オレのモノを突っ込んで…。
かなり獣の気分。
「ちょっと、何かエッチな事考えてるだろ、海里」
「当たり。これからの取材にはちょうどいいじゃん。なにせエロ雑…」
「その言い方やめてくれないかなあ」
「後で雑誌送るんだっけな」
「やめたほうがいいと思う?」
「いいじゃん、送れよ。ビックリするだろうけど。でもまあ…とりあえず」
あの写真が載った雑誌が2人の手元に届く。
それはちょっとだけ宣戦布告な気分だった。
秘密のリゾート後編へ

|